Satsuma, S. Britain and Colonial Maritime War in the Early Eighteenth Century: Silver, Seapower and the Atlantic.Boydell & Brewer, 2013, 284p, 978-1843838623.
※この本はEconomic History Review や Journal of Imperial and Commonwealth Historyなど海外を中心とする十誌に及ぶ学術誌で書評されました。
海上で他の船を襲って積み荷を奪う、こう聞くとそれは犯罪行為では?と思う人も多いのではないでしょうか。しかし、16~19世紀初頭のイギリスを含むヨーロッパの国々では、政府の認可を得て戦争中に敵船を合法的に略奪することが許されていました。また、16世紀の略奪の成功体験を基に、近世イギリスでは、広義の海軍力の行使は利益をもたらすという議論が議会やメディアで見られました。本研究はこのような近世における海での戦いと利益獲得の結びつきがイギリスの政治や外交にいかなる影響を与えたのかを探っています。

薩摩 真介(さつま しんすけ)
准教授
大学院総合科学研究科 地域研究講座
研究分野 人文学 / 史学 / ヨーロッパ史・アメリカ史
私が研究しているのは、近世ヨーロッパ、特に18世紀のイギリスにおける海上での暴力(広義の軍事力)の行使と利益獲得の関係です。近世(16~19世紀初頭)のイギリスを含むヨーロッパの多くの国々では、海上における暴力行使は経済活動の側面も持っていました。例えば、海軍の軍艦や民間の船が敵商船を拿捕して、その積み荷を売却することで利益を得るということが行われていました。それだけでなく、一定の制限内であればそれは合法的な行為とみなされていたのです。海戦を含む海上での暴力行使と利益獲得のこのような強い結びつきは、近現代の戦争と比べた場合の近世の戦争の特徴の一つと言えます。しかし海軍史家は近世の戦争におけるこのような利益獲得の側面にはあまり注意を払ってきませんでした。それは海軍史家の関心が主として18世紀のイギリス海軍の成功の理由を探ることに向けられていたからです。しかし、近世の海上での戦争の全体像を把握するには、この利益獲得的側面を無視することはできません。

サー・フランシス・ドレイクの帆船「ゴールデン・ハインド」号実物大レプリカ(St Mary Overie Dock, London)
Copyright (c) Diego Delso, delso.photo, CC BY-SA 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
私は、このような海上での暴力行使と利益獲得の歴史的結びつきを、次の二つのトピックにおいて分析しています。一つ目は民間人による略奪行為、すなわち非合法な海賊行為および合法的略奪とされた私掠(しりゃく)行為の統制の歴史です。二つ目は海軍力の行使はイギリスに様々な利益をもたらすという当時なされていた議論に関わるもので、本書で扱っているのは後者のほうのトピックです。
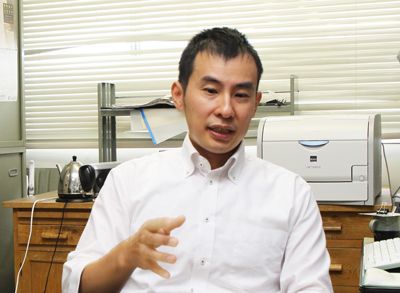
近世のイギリスでは、海戦こそが理想的な戦い方であるとの議論が当時の議会やメディア上で見られました。私が「海戦支持の言説」と呼んでいるこの議論は、16世紀後半のエリザベス女王期の航海者フランシス・ドレイクらによる略奪活動に起源を有し、その後19世紀初頭まで、スペインとの戦争が起こるたびに蘇りました。これまでこの議論はもっぱらイギリスの政治党派対立や戦略論の文脈で分析されてきました。しかし、この議論がなぜ党派を超えた支持を得たかについては十分説明されてきませんでした。その理由を探るため、私は議論の中核となる要素、すなわちスペイン銀船団の拿捕や中南米のスペイン領植民地征服といった、海軍力を行使することで得られると信じられていた経済的利点に注目しました。これは当時見られた海軍力の積極的活用を訴える議論の多くに共通する要素であり、この議論が異なる政治党派を惹きつけた理由であったと考えられます(もっとも、そのような経済的利点の多くは実際には誇張されたものでした)。

サー・フランシス・ドレイクの帆船「ゴールデン・ハインド」号が描かれた10進法移行前の英国のコイン
私は18世紀初頭の時期におけるこの議論とその影響を、当時刊行されていたパンフレットや新聞類、政治家の手紙、行政文書などの史料を分析することで探りました。そして、この分析を通じて、当時、海戦には具体的にどのような経済的利点があると考えられていたのか、この議論は当時のイギリスの政治家にいかなる影響を与えたのか、どのような経済的利害集団がこの議論を支持したのか、そして議論の内容が状況の変化に伴いどう変容したのかといった点を明らかにしました。それによりこの「海戦支持の言説」のより包括的な像を提示し、近世の海戦と利益獲得の結びつきが当時のイギリスの植民地拡張や実際の政治・外交政策にいかなる影響を及ぼしたのかを考察しました。この研究を通じて近世ヨーロッパの戦争の特徴の一端を明らかにすることは、現代における戦争の様態の変化を考える上でひとつの材料を提供できるのではないかと考えています。

この記事は、学術・社会連携室と広報グループが作成し、2017年に公開したものです。

 Home
Home