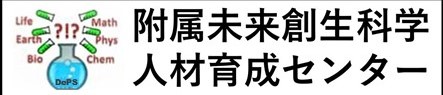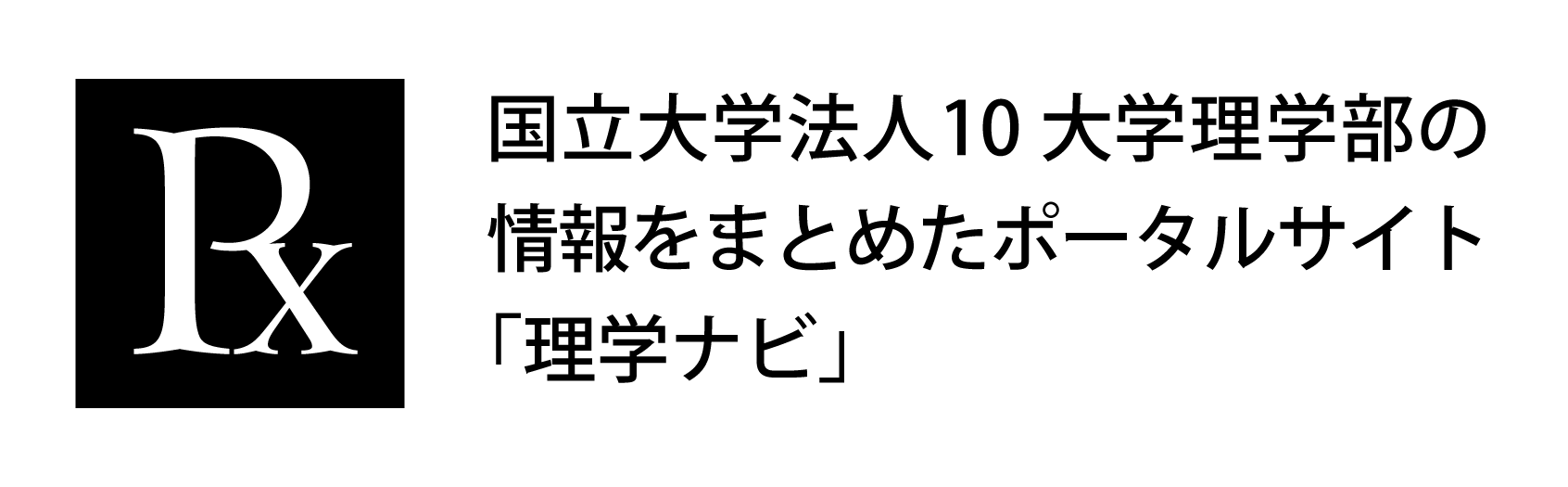私の研究者人生:大野 啓一(化学専攻)
氏名:大野 啓一
専攻:化学専攻
職階:教授
昨年度より本研究科ホームページに「私の研究者人生」の連載が始まった。今年度は、定年を迎える私が仰せつかった。多くの方に助けられた研究人生で、研究には紆余屈折があるが、私のつたない経験を、研究生活に沿って思いつくまま書かせて頂く。
大学生時代(1962−1968)
1962年春、今も変わらぬ市内電車に乗って、初めて東千田町の広島大学理学部に受験のためにやって来た。木造の高等学校で学んだ私にとって、レンガ作りの重厚な建物に圧倒された。何とか合格し、この1号館で学ぶことになった。4 年次には隣に新築された2号館に移り、高分子化学講座(村田弘教授、林通郎助教授が在籍)で卒論と修論に取り組んだ。振動分光法を専門とする研究室であったので、直ちにタイガーの手回し計算機で1,2-ジクロロエタンの基準振動計算を命じられた。卒論では、京都大学の林宗市先生のもとで単結晶の作り方を学び、赤外用窓材の岩塩(KCl, KBr)を自作できるようにしたことを報告した。修士課程では、林通郎先生が留学先で研究されたマイクロ波分光の装置作成に加わった。日本放送協会のラジオ技術教科書を独学し、ハンダ鏝で回路を組み立てた。装置の立ち上げに参加することで、装置をうまく使いこなせることを身をもって感じた。以後、装置の搬入時には必ず立ち会うことにしている。この装置で、直ぐに未知分子の測定に取りかかった。しかし、膨大な数のバンドは観測できるが一向に帰属ができない。結局、初心に戻り、先ず既知分子を用いて、装置の設定条件と電場をかけた場合のバンドの挙動や分裂の仕方などを知っておくことが必須であることを悟った。急がば回れである。次に、分子の精密構造(rs構造)を決定するには、分子の特定の水素原子を一つずつ重水素で置き換えた試料の合成が必要であった。そこで、重水素化ができそうな合成ルートを文献で調べ、最も簡単に合成ができるルートを探すことに2年間明け暮れた。ここでも、先ず予備実験で自分の合成能力を確かめることが先決であった。この重水素化の技術が、私のこれからの研究の重要な位置を占めることになるとは、その当時は思いもしなかった。
教官・教員時代(助手:1968−1988, 助教授:1988−1999, 教授:1999−2007)
修士修了後、他大学へ就職が内定していたが、何故か1968年4 月よりそのまま助手に採用して頂けた。新しい現象に一番先に出合える仕事をして生活できることが非常に嬉しかった。1年間順調に実験データが出始めた矢先に大学紛争が広島大学にも波及した。 1969年5月には、広島大学は封鎖され研究ができなくなったが、大阪大学蛋白質研究所、宮澤辰雄研究室に半年間共同研究員として学ぶことができた。そこで新進気鋭の菅田宏、北川禎三両先生に、GF行列の計算プログラムを教わった。その後、広島大学に戻ったが紛争の後遺症でマイクロ波分光の再開が伸び伸びとなっていた。助手ということで学位をとる必要に迫られた。ちょうど、当時としては高価な赤外分光計Perkin-Elmer 621が研究室に納入された。有機ケイ素化合物の合成も行っていたので、その振動スペクトル解析と回転異性を学位論文のテーマとした。エチルメチルシランでの回転異性の存在の可能性を示したが、先生方には、なかなか受け入れてもらえなかった。回転異性体の存在が世界で初めて確証されたのは、1934年、東京大学水島三一郎先生らの1,2-ジハロゲノエタンの振動分光による研究である。以来、水島・島内研究室で精力的にC−C結合回りの回転異性の研究がされていた。門下生の林先生はC−S結合回りの回転異性の発見で知られ、次にC−Si結合回りの回転異性に取り組まれていた。また、村田先生も独自に同様の研究をされてきていた。しかし、このC−Si結合は、C−C結合よりも結合距離が長いため、古典的な計算からは拘束回転でなく“自由回転”していることが当時の常識となっていたようである。しかたなく、類似化合物について調べていたところ、運良く(クロロメチル)メチルシランで、急冷と徐冷による固体で異なる赤外スペクトルを得た。この結果、回転異性体が存在することが疑いないものとなった。残念ながら、C−Si結合回りの回転異性の存在は、1966年に(クロロ)エチルシランを用いてソ連の科学者により発表されていた。(クロロメチル)クロロシランと関連の化合物の結果をまとめて、1975年に理学博士(広島大学)の学位を得た。このような研究には、レーザーラマン分光計が赤外分光計よりも有効で、当初は大阪大学の宮澤研で装置を借りて実験していた。 1974年、待望のレーザーラマン分光計が研究室に導入され、本格的に回転異性の研究ができるようになった。C−Si結合では先を越されたので、何とか人より早くということでC−Se(1976)、Si−O(1979)、Si−S(1980)、Si−Si(1983)、C−Ge(1985)軸まわりの回転異性を報告した。
1973年、林通郎先生が構造化学講座の教授に、1976年末に、村田研出身の松浦博厚先生が講師として東京大学より戻られた。1978年に、研究室に日本製としては最高の高分解能赤外分光計 JEOL JIR-40Xが研究室に導入され、より精度の高い研究ができると喜んだ。
学位取得後、外国に留学するのが一般的な風潮であったので、苦手な英会話を習わなければならなくなった。何時かやることになるのなら、中学・高校時代に真面目にしておけばよかったと後悔したが後の祭りである。とにもかくにも、大学の裏手にある英会話学校に夕方通うことにした。英会話コースを半分程度終えたころ、林先生より博士研究員として雇ってもらえそうな研究室があることを知った。私でもやれそうな研究室であったので手紙を書いた。
それが英国サセックス大学のKroto研究室であった。研究内容は、新奇な炭素—リン多重結合をもつ分子のマイクロ波分光による同定であった。この化合物は、1961年GierによってHC≡Pが発見されているのみで、以後、関連の報告はなかった。 Kroto先生は、1976年にCH3C≡P, CH2=PH など一連の化合物を同定し、この分野を開拓していることで知られていた。私の役目は、この分野をさらに発展させるためで、1979年9月末に到着するとすぐに私の研究したい化合物を聞かれ、それらの内、興味のある化合物の合成に取り掛かった。既に、大橋修先生(上智大学)が博士研究員として同室に在籍されていた。大橋先生からのアドバイスのおかげで、研究面、生活面全て何の支障もなく快適に過ごすことができた。雑用が一切なく、英国人が習慣としている午前と午後のテイータイムを楽しみ、5時過ぎには帰宅するという優雅な研究生活ができた。ここで、CH2=CHC≡P, HC≡CC≡P, PhC≡Pを見つけ、部分重水素化の技術の助けでCH2=PH、CH2=PClの精密構造も決定した。
1981年3月、私が帰国するときに、Kroto先生は、これら一連の短寿命リン化合物の研究に目処がついたので、合成面で研究が頓挫していたもう1つの脚光を浴びていたシアノポリインH(C≡C)nC≡Nの研究に戻りたいと話された。後に聴いた話によると、これが1985年のC60の発見につながったとのことある。身近な人のノーベル化学賞受賞は誠に嬉しいかぎりである。
帰国後、HC≡P以外皆無だった炭素—リン多重結合をもつ化合物の詳しい振動スペクトルの解析に着手した。一連のリン化合物の振動スペクトルを解析し、炭素—リン多重結合の振動数と力の定数を求めた。また、理論計算より、ほぼ全ての伸縮振動に適応できる簡単な力の定数と結合距離の関係式(Badger’s model)を得た。一方、既設の高分解能赤外分光計(JEOL JIR-40X最高分解能0.08 cm-1)を用いて、FC≡P, CH3C≡Pについて振動・回転スペクトルを解析した。解析には林研究室の中川潤先生に助けて頂いた。しかしながら、共同研究していたKroto研究室の Bomem DA3.002 赤外分光計(最高分解能0.01 cm-1) で測定したCH3C≡Pのスペクトル結果をもらい精度のよさに愕然とした。結局、これを用いた解析に切り替えることになった。短寿命化合物の高分解能振動・回転スペクトル解析のような研究は、常に最高機種が購入できる大学でないとやっていけないということを痛感した。また、短寿命化合物の気体状態の測定がかなり困難であったこともあり、これらを極低温の希ガスで閉じ込めて測定を行う極低温マトリックス単離赤外分光法による研究に向かうきっかけとなった。このマトリックス単離による研究は、1992年ころに科研費を得てやっと開始することができた。
この間、1983年には、村田先生が退官、1988年に松浦先生が教授に昇格され、1ヶ月後、私も助教授となった。1988年に当時研究室の院生だった福原幸一さんが、1991年に東大から吉田弘さんが、それぞれ助手として採用された。また、理学部も1991年夏に広島市東千田町より東広島市鏡山に移転し、2度目の研究室の移動を体験した。
1983年、私の部分重水素化の技術を買われ、岡崎にある分子科学研究所の廣田榮治研究室の協力研究員となり、遠藤泰樹先生のもとで実験した。ここには、自作された高感度のミリ波のマイクロ波分光計があった。シラン、ゲルマン、スタンナンのマイクロ波スペクトルは通常の状態では観測できない。部分重水素化により永久双極子を僅かに生じさせることにより、これらの分子の吸収を観測できた。
一方、これまで研究してきた分子のコンホメーションを決める基準振動計算は、実測の構造と類似化合物より求めた経験的力場を用いて行われていた。したがって、1990年ころまでは、特に未知化合物の構造や力の定数を推定することは至難の技であった。吉田助手が当研究室に持ち込んだ ab initioの理論計算からえられる分子構造と非経験的力場を用いた基準振動計算が、実測の振動スペクトルとかなりよく対応することに驚いた。1980年代からのコンピュータと理論計算の進歩は凄まじく、短期間にレベルの高い計算が高速でできるようになってきた。特に、極低温マトリックス単離赤外分光法から得られる情報は、孤立分子の真空状態に近い結果で、直接、理論計算と比較でき、非常に明快な結論が得られるようになっていった。早速、この長所を生かして極低温マトリックス単離赤外分光法と理論計算法を併用して、分子のコンホメーション状態を調べることにした。計算結果から、当時予想もしていなかった弱い分子内相互作用が、特定のコンホメーションを安定化していることを明らかにできた。1997年ころには弱いCH…O, CH…N, CH…π 分子内相互作用の存在が確かなものとなっていった。さらに、希薄溶液、液体、水溶液の実験とこれらの手法を組み合わせ、分子内・分子間相互作用の競合や強い分子内NH+…O, NH+…N 水素結合が存在していることが分かった。また、2005年には、この手法を用いて水のクラスター、希薄溶液、水溶液、氷のOH 伸縮振動と水素結合様式の関係を調べた。OH 伸縮振動の波数と水素結合に関する研究のように過去に非常に多くの報告があり、今更何も新しいものはでてこないと思われるような研究対象でも、新しい手法で見直すと何か得るものがあることを知った。
1984年、孤立C−H伸縮振動の波数は、アルキル基のコンホメーションにより異なることを示す論文がSnyderらにより発表されていた。しかし、このような重水素化物の合成は困難で、なおかつ非常に高価となる。一方、孤立C−D結合をもつ化合物は比較的容易に合成でき安価であることに気付いた。そこで、孤立C−D伸縮振動をキーバンドとするコンホメーション解析を手がけた。この孤立C−D結合をもつ化合物は、重水素NMRでも測定でき、液晶中の分子の構造を調べるキーバンドとしても利用できることを知った。幸いにも、重水素NMRを研究されていた奥田勉教授、山田康治助教授に教えを請い、1999 年、両者を併用した非イオン界面活性剤への研究に発展させ、孤立C−D結合を利用した振動分光・核磁気共鳴による構造解析を行った。また、C−H伸縮振動は水溶液中で高波数シフトすることが知られていたが、その要因はよく分かっていなかった。この要因を調べるために孤立C−D伸縮振動をキーバンドとして利用する手法を、2003年に研究グループに加わった勝本之晶助手とともに手がけた。それぞれの位置の孤立C−D伸縮振動シフトを測定する手法で、有機分子と水との関わりを明らかにすることができ、この方面へのさらなる展開をはかっている。
1999年、新設の分子反応講座集積化学研究グループの教授に昇任し、2001年、岡田和正助教授がグループに加わった。2003年に、光照射が可能な高圧水銀灯を購入したことと、2004年に赤井伸行博士研究員の参加で、これまでの分子の静的な情報だけでなく、念願の動的な反応機構を追えるマトリックス単離赤外分光実験ができるようになった。この結果、DNA塩基のさまざまなモデル化合物に紫外線を照射すると、ケト—エノール互変異性化に加え、アミノ—イミノ互変異性化が生じることが分かった。やっと目標としていた装置が一通り揃い、反応機構の動的な研究が軌道に乗ったところで定年を迎えることとなった。
これらの研究成果は、前述の多くの先生方のご指導、学生諸君の献身的な努力、職員の方々の器具作成や寒剤提供によるご援助ならびに理学研究科教職員の皆様の温かいご支援の賜物です。この場をかりてこれらの方々に心から感謝するとともに、厚くお礼を申し上げます。本理学研究科は、私が幸運にも体験することのできたように、役に立つかどうか分からない基礎研究を、自由な雰囲気で自由にできる環境であり続けて欲しいと心から願っています。

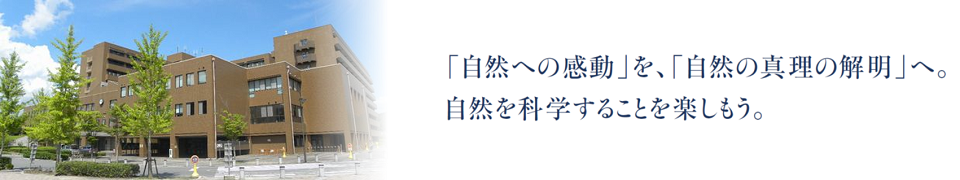
 Home
Home