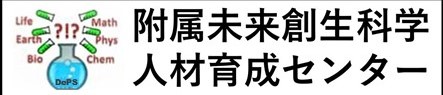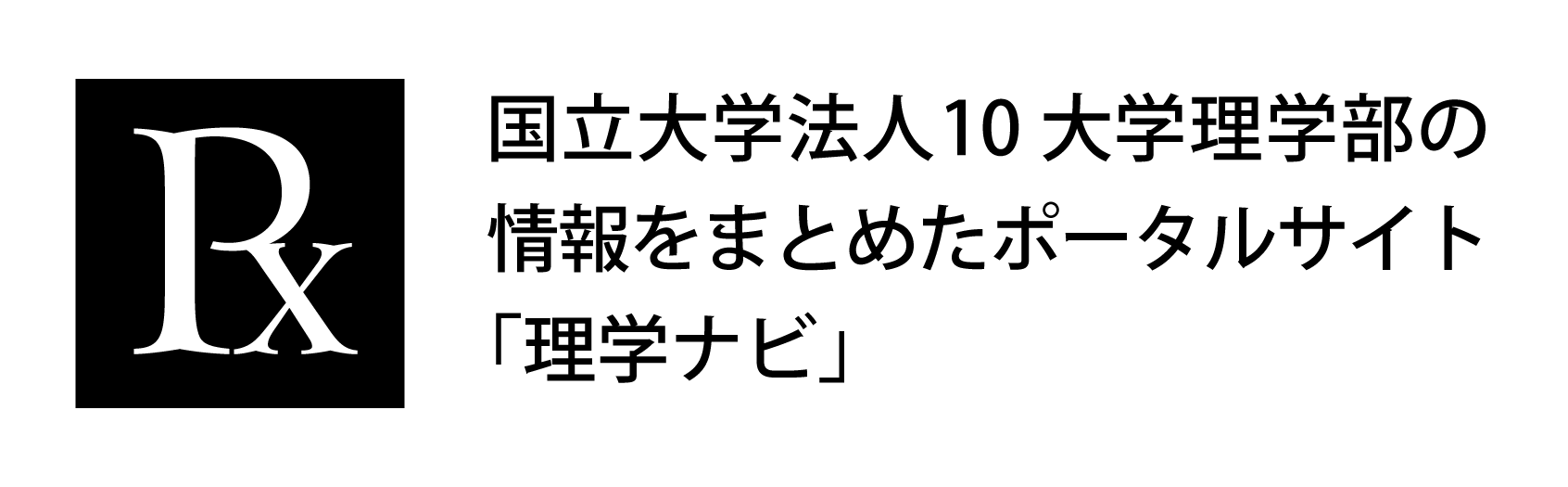私の研究者人生:深澤 義正(化学専攻)
氏名:深澤 義正
専攻:化学専攻
職階:教授
はじめに
定年退職を半年後に控える頃に広報委員会から、これから研究者をめざす若者をエンカレッジするため「私の研究者人生」という記事を書くように依頼を受けた。有機化学が好きで、有機化合物の構造の美しさに魅せられて、有機化学を中心に研究活動を楽しんで続けてくることができ、大変恵まれた研究者人生であったと思っている。こんな筆者のささやかな経験を披露することがはたして広報委員会の目的に適うものであるか甚だ心許ないが、研究活動の一端を披露してその務めを果たすことにしたい。
学生・大学院生時代
昭和37年、東北大学理学部に入学した後に化学を選び、街中にある片平キャンパスで講義と学生実験に明け暮れしていた。3年生になり配属を希望していた研究室の伊東 椒教授がハーバード大学のWoodward研で博士研究員をされていた時の研究であるクロロフィルの合成に関する解説記事が新刊の「新しい化学」という本の中に書かれているのを見付けた。有機合成でノーベル賞を受賞したRobert Burns Woodward教授が葉緑素であるクロロフィルの有機合成に挑戦し、さまざまな問題点を解決し、ほぼ完成に近づいた時に「今年は自然に負けたが、来年は勝つぞ」と言われたと記載されていた。若者には感動的であった。これを読んだことがその研究室を希望する気持ちを益々高めた。幸い希望した研究室に無事配属された。当然のことのように卒業研究では天然有機化合物の有機合成を希望した。直接には竹下 斎先生(当時講師、後に九州大学機能物質科学研究所教授)にご指導いただいた。当時の自分の知識と実験の腕では、どんな簡単な天然物でも卒業研究で容易に合成できるとは思っていなかったが、案の定、卒論発表(当時は3月15日と決まっていた)の1ヶ月前に研究テーマが「クパレンの合成の試み」から「カンファーの光分解」に変わった。それからは連日徹夜に近い状態を経て無事卒論の発表を終えた。
卒論が終わった後も連日、光反応生成物の分離精製の日々が続いた。単調すぎていささか継続に対する根気を失いかけた修士1年の9月に、X線解析を習うため東京大学薬学部に派遣され、飯高洋一教授のご指導を受けることになった。当時のX線解析は現在とは違い、化合物にハロゲンなどの重原子を含むことが必要であったし、データも多重フイルムに露出された反射スポットの強度を目測して集めた。この過程が大変で通常一、二ヶ月を要した。この強度データを、当時やっと大学に導入されはじめた大型計算機を用いて処理するのであるが、計算センターに計算を依頼してから結果を得るまでに4、5日待たされるのが常で、一つの構造を解くのに順調にいったものでも三、四ヶ月かかるのが普通であった。この待ち時間を利用して、X線解析のプログラムの流れを解読することに努めた。現在、自作のいくつかのプログラムの利用価値が認められ公開せよと言われるのも、この時の勉強が役に立っているのかもしれない。
他大学に行って、違った分野の研究に従事し、一応の成果を得ることが出来たことは、全く違った研究分野に飛び込む勇気を与えてくれた。この経験はその後、研究活動を広げるのに大いに貢献した。修士論文は英語で書いた。研究室は違ったが、入学以来の友人で同じ化学を学び、現在大阪大学工学部応用物理学科の教授である増原 宏君に刺激されたのが原因である。原稿は伊東先生によって原文が全く無くなるほど直されたが、このときの経験は役に立った。仙台に帰って博士課程の研究として、X線解析を武器に、非ベンゼン系芳香族化合物の構造解析を行った。本来平面である芳香族化合物は、嵩高い置換基が導入されると非平面へ変形するが、その変形の様式をより深く理解するため、当時有機化学者にはまったく注目されていなかった分子力学計算について文献を調べた。幸いプログラムを恵与してくれる研究者(Uhta大学のBoyd教授)があり、それを自分でカードにパンチして使った。しかし、当時は現在のようにほとんどの分子に使える汎用性のあるパラメータは組み込まれておらず、赤外線分光法の振動解析の論文を探しては適当なパラメータを求めて計算したが、思わしい結果は得られなかった。したがって、この計算による実測の構造を再現する試みは、残念ながら博士論文に掲載することはできなかったが、この努力は全くの徒労に終わったわけではなく、後の研究の方向を決めるのに役立った。博士論文の研究の終盤に、複数個の化合物のX線構造解析を終えてデータを整理したところ、非ベンゼン系芳香族化合物の共鳴理論を説明できる、C−C結合距離の結合交替に関する法則らしきものを見出すことができた。これはベンゼンのC−C結合距離の結合交替に関するMills-Nixon効果の謎解きにも相当することに思い当たった。この原理を発見し、それで全てのトロポロンの互変異性体平衡が説明できることを見出したことは、その後の研究に対する意欲をいやが上にも高めた。この発見は些細なことではあったが、いままで多くの先達が居るにも拘らず、そのような観点からの報告がなされていなかったことから、自分でも研究の名に値する発見などができるのではないかと思うと共に、化学の研究の魅力を改めて感じ、研究活動を行っていく自信を深めるのに非常に役に立ったと思っている。これが化学の研究の魔力に魅入られた第一歩で、その後の研究のモチベーションになった。
博士研究者時代
当時でも今と同様アカデミックポジションは狭き門で、同じ研究室で博士の学位を取得した2人の同級生をふくめて3人とも、国内での職を見つけずに(または見つからずに)、外国の博士研究員になるべく出国した。最近では、国内に職を得てから博士研究員として外国に出る場合が多いが、当時のオーバードクターの方が向こう見ずだったのかもしれない。筆者は学部学生の時の研究テーマに近い天然有機化合物の構造研究をするため、カナダ、アルバータ大学Ayer教授のもとで、1972年の秋から博士研究員として1年9ヶ月を過ごした。得意のX線結晶解析を武器にリコポジウムアルカロイドの構造解析を行った。博士研究員は身分的には不安定で、すぐ次の職を探さなければならないのが欠点ではあるが、時間的には非常に恵まれた職で、会議や後輩の指導、講義などが全く無く、研究一筋の生活をすることが許された。この豊富にある時間を利用して将来の進むべき道を模索したが、必ずしもアカデミックポジションにつける保障があるわけでもなかったので、不安定な気分ではあった。幸い、カナディアンロッキーのスキー名所であるバンフにも近かったこともあり、趣味のスキーも充分に楽しみ Dull boyにならないように努めた。
筆者の学部時代にやっと日本の大学にも大型計算機が導入されたのであったが、その後の計算機の発達は早く、博士研究員をする頃までにはX線結晶解析の分野でも、測定装置の自動化が進み、データ収集も非常に容易になっていた。このような状況下では構造解析の手段に用いたX線結晶解析の威力は大きく、構造解析に費やす時間を一気に短縮できたが、同時にその便利さがより有効な解析プログラムの開発を促し、コンピュータの発達と相俟って、近い将来に一般的な解析手段として、実験化学者が専門家に頼らずに自分でX線解析を行えるようになるであろうことを予感させ、X線結晶解析のみを専門にすることに不安を感じ始め、X線結晶解析を武器として利用するための最適な化学の分野を模索し始めていた。
東北大学時代
幸いなことに出身研究室の助手に採用していただき、1974年に再度、学生時代の指導教授と協同研究させてもらえる機会を与えられた。博士課程後期在学中に前述のWoodwardと後にノーベル賞を受賞したR. Hoffmann博士により軌道対称性の保存則に関する大作が論文として掲載された。この研究は彼のノーベル賞受賞に大きな寄与をしたものであり、有機化学反応に分子軌道の考え方がいかに重要であるかを示したが、その日本語訳を出身研究室の先生方が出版した。その際のささやかなお手伝いも、助手に採用されたことに多少は寄与しているかもしれない。助手になったことを機に、天然有機化合物に関する研究から撤退し、研究テーマを構造有機、非ベンゼン系芳香族化合物の合成と構造、性質を研究する化学に絞ることにした。当時の研究室ではシクロファンの化学が始まったところであったので、この分野との合体を図ることにした。対象としたのは非ベンゼン系芳香族化合物を含む短架橋のシクロファンであった。アズレノファン、トロポロノファン、トロポノファンなど多くの化合物を合成し、その性質を調べた。芳香族化合物の環電流効果を評価する方法について研究し、計算プログラムを書き上げた。このプログラムを完成させたことが、その後の核磁気共鳴における化学シフトを利用して立体配座解析を行う独自の研究領域開発の基礎となった。助手になって9年後に広島大学へ移ることになった。広島へ行く2ヶ月前の1983年1月に、東北大で助教授に昇任した。
広島大学時代
1983年3月に広島大学に移った。広島でも助教授で研究を開始した。所属した研究室は変則で、助教授2、助手2の構成であった。赴任した研究室出身の笛吹 修治博士は教務職員をしていた。研究分野はかなり違っていたが、助手になってもらって、職員が二人の小さいながらも独立した研究室を立ち上げ新しい研究をはじめることができた。新たに光化学反応(光SRN1反応)を用いるシクロファン合成を始めた。新しい研究課題はすぐには軌道に乗らなかったが、職員、学生の努力で少しずつ成果が出ていった。1983年に東京で開催された国際会議で、後に友人となったコロンビア大学のW. C. Still教授の講演を聞いたことがきっかけとなって、フレキシブルな大環状化合物の構造解析に分子力学計算手法を用いることを思いつき、そのための初期配座発生プログラムを自作した。このプログラムの威力は強力で大環状シクロファンに留まらず、大環状天然物の立体配座の研究に大いに役立った。勿論、博士課程で独学した分子力学計算法は構造解析の手段として利用したが、このときにはこの手法も非常に洗練されてきており、信頼性は非常に大きかった。
その後、仙台時代の研究室の後輩であり、現在東京工業大学理工学研究科教授の高橋 孝志君から、大環状化合物の渡環反応に関する相談を受けた。かねてから分子力学計算の応用範囲を拡大する意味で、遷移状態モデリング法を考えていたので、渡りに舟とばかりに大環状化合物の渡環反応へ遷移状態モデリングを適用する研究を始めた。14員環内のDiels-Alder反応によるステロイド骨格合成の際の立体選択性に遷移状態モデリングを適用したところ、非常にきれいに実測の選択性を説明することができ、この分野の最初の輝かしい成果となった。これに味を占めて、既知の遷移状態構造を使うだけでなく、自分で種々の有機化学反応の未知の遷移状態構造を求める研究も開始した。[2,3]Wittig反応や、ペンタジエニルカチオンへのアルコールの付加反応などの遷移状態の構造を決定し、実際に大環状化合物の立体選択性を解析することに成功した。
大環状シクロファンの構造解析の拡張としてカリクサレンの化学を始めた。カリクサレンは分子認識のためのホスト分子として注目を集めており、多くの先駆者がいたため、独自の領域を開発すべくカリクサレンから一つOH基を取り去った化合物の立体配座解析から始めた。結果的にはこの化合物もホストとして機能したことから、必然的に分子認識の化学へと進んでいくことになった。ホスト分子としては、有機小分子ゲストの捕捉のため、空孔が必要であるので、単純にゲストが適合する大きさの空孔さえ用意すれば事足りると考えていたが、ホストとゲストの間に疎水性相互作用が働く水中での捕捉ならいざ知らず、有機溶媒中では溶媒分子もその空孔を占領するため、有効なゲスト捕捉ができなかった。そこで溶媒が入ってこられない非溶媒和空孔を利用する超分子化学の研究を行った。しかし、これだけでは溶媒分子より大きな分子を取り込むのは困難であったので、非常に大きなゲストとの一例としてフラーレンを選んだ。ホストとゲストの接触面積を増やすことで溶媒和に打ち勝つ事が出来ると考えて、ホストを選んだところ、フラーレンを有機溶媒中で効率よく捕捉することに成功した。この研究で溶媒和、脱溶媒和がいかに重要か再確認させられた。常日頃から学生には「化合物に教わりなさい。人間の知恵などまだまだだから」と言っていたが、この場合もそうであった。
これらの超分子化学に関する研究の他、フレキシブルな構造をもつ分子の、溶液中での可能な全ての構造をいかに正確に求めることができるかが、常に気になっていた。このことは、博士論文の研究で有機化合物の構造に魅せられたことと密接に関係しているものと思っている。まさに「三つ子の魂百まで」と言ったところか。以前からも、その解析手法として核磁気共鳴における化学シフトを利用する研究を始めており、芳香環の環電流を用いる化学シフト計算法を用いてシクロファンの構造解析を行ってはいたが、環電流効果だけでは対象が限定されてしまうので、各種の極性官能基に基づく誘起磁気遮蔽効果を見積もる必要を感じていた。たまたま広島に移って間もない頃、物理が得意な学生が研究室に入ってくれたので、彼にカルボニル基の磁気遮蔽効果を求める研究課題を渡したところ、見事な成果を出してくれた。この成功に刺激され、その学生が研究室を離れた後に、中国からの留学生と一緒にエーテル、エステル等の磁気遮蔽効果を求めた。最近では分子動力学計算を用いて、溶液中で分子の熱運動を考慮したプログラムを書き上げ、化学シフト予測法として、その応用範囲を広げつつある。
この手法は特に、超分子錯体の溶液における構造解析の強力な武器であり、超分子錯体の溶液中の構造解析には無くてはならない手法になりつつあるものと思っている。この手法の応用範囲は広く、複雑な構造をもつ生体高分子の構造解析への応用も期待できる。現に限定的な利用ではあるが、生体高分子、特にタンパク質の溶液中の構造解析に利用している研究者が出てきている。我々は化学シフトを利用した動的構造論の創製と題してこの研究を発展させつつあるが、残念ながら、現役の研究者生活も残すところあと数ヶ月になってしまった。一人の人間が出来ることはたいしたことではないが、とにかく有機化学が好きであることと、その好きな有機化学の研究を好きなだけ続けてこられたこと、その上、研究活動の途上たびたび「わくわくする」ことに遭遇できたことは、研究者冥利に尽きるのではないかと思っている。このような研究活動ができたのも、よき指導者、よき友人達や有能な共同研究者に恵まれたことと、昼夜を分かたず献身的な研究に励んでくれた多くの学生諸君のお陰と思って感謝している。最後に広島大学大学院理学研究科が益々発展されんことを祈って拙文の終わりとしたい。

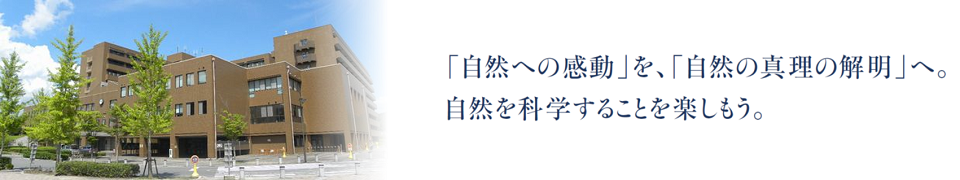
 Home
Home