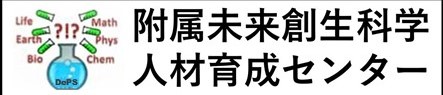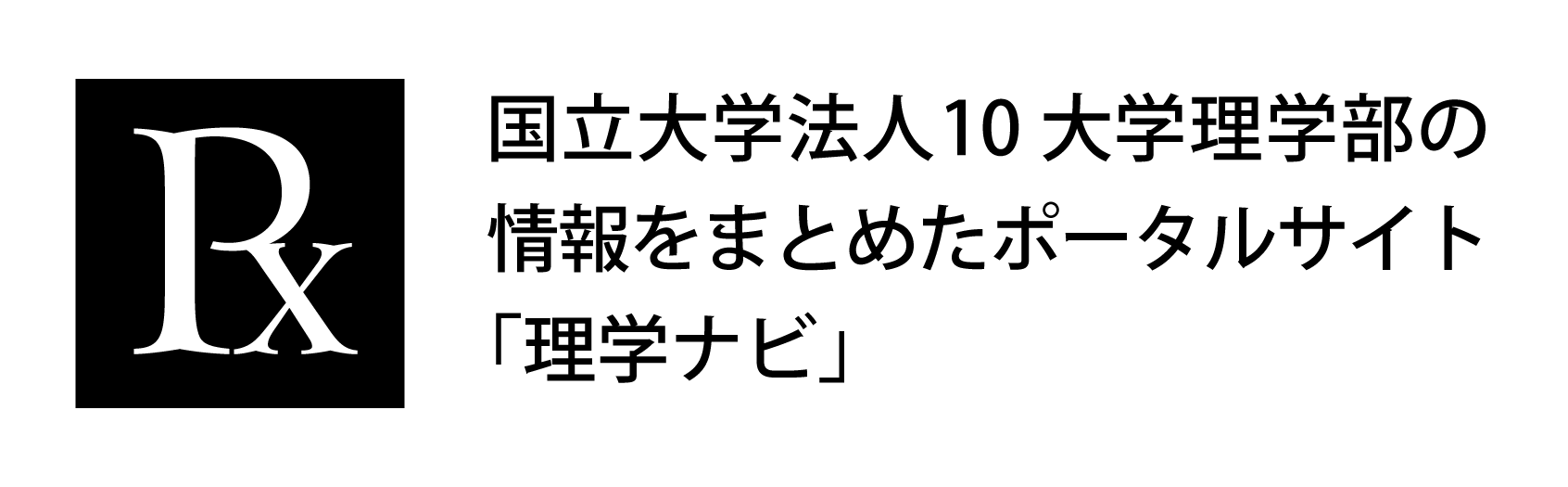アイセル湖の夕暮れに向かって珈琲を頂く私(2001年)
数理科学者は如何にして鍛えられるか?
氏名:大西 勇
専攻:数理分子生命理学専攻
職階:准教授
専門分野:系の非線形性と関わる問題の解析
略歴:大学院理学研究科助教授。博士(数理科学)
1964年大阪府藤井寺市生まれ。早稲田大学理工学部数学科卒業、東京大学大学院数理科学研究科博士課程(後期)修了。
電気通信大学電気通信 学部助手、講師を経て、2001年度より現職。
専門は、特に、生命現象によって構成される系の非線形性と関わる問題、もしくは、そこに内在している数理的な構造の解析。
単なる微分方程式論の「応用」といった感覚でなく、数理科学として興味深い構造が示唆されるような「現象」をヒントに、自分なりの理論を組み上げていくような仕事に興味がある。モデリングから解析までがスローガン。
最近は、 細胞レベル、分子レベルでの生命現象をヒントにそこに隠れている数理構造の解析をしてみたいと思い、勉強中です。
趣味は、コンピュータに関する何か?AT互換機の自作とかもします。最近は、自宅サーバで、TVサーバの構築をしたりしてます。自宅はCATVなんで、遠くいるときでも、自宅のTVを見られるようにしたいです。好きなOSはSUSE Linux。最近、Nov○l が、マイ○ロ○フト と「提携」するらしく、大いに不安です。
なぜ数理科学の研究者になろうと思ったのかな?と、今回考えて見ました。12歳くらいまでは、特に、喘息がひどかった私は家で一人でいることが多く、NHKの理科教室なんかをみていると「不思議だなぁ」とかは思いましたが、数学については普通の興味しかありませんでしたしね。家にいて午後になるとTVがつまらなくなるので、よく本を読みました。
子供のころは推理小説。何か謎を解いていくというようなストーリー展開が好きなのかも知れません。しかし、高校生になるころには純文学へ。三島由紀夫とか白樺派とか。あまり系統なく、暇にまかせて読んでいる感じでしたかね?大学からは一人暮らしでした。いろいろ精神的にきつくなってくると同時に、本の好みも変わって、純粋なものより、現代アメリカものみたいなのが好きになっていきました。レイモンド カーヴァーとかポール オースター、海外で時間が多くあるときとかは、ディッケンズなんかを持ち歩きました。ジャック ケルアックなんかも面白いと感じるような精神状態になっていきました。何かある種の状況と「才能」の葛藤とか、極限的な「何か」を感じたいというような、そういう状態だったのだと思います。もちろん、当時、このような分析的な思考を行っていたわけでなく、「あ、これは俺の読むべきものだ」と思っていたに過ぎませんけれども。
大学は数学科に進学したので、数学の勉強をしました。これはこれでなかなか興味深いものです。数学は人間の頭の中でのみ意味を持つもので、その出自的には、自然科学とは関係がありません。ただし、人間の自然認識の形態が数学的な構造を持つものであったから(だからこそ、数学は人間にしか意味をもたないわけですが)、それを記述言語として用いて、自然科学が発展しました。1年生のときは、代数学にはまっていました。2年生のときは幾何学、特に、代数的な幾何学をやってみたいと思うようになっていました。早稲田では3年生の後半に卒業ゼミに付くのですが、そのころにはなぜか気が変わって、解析学(特に、偏微分方程式論)を専攻される方に師事させて頂きました。なぜ気が変わったか、明確には思い出せません。「縁」があったのでしょう。「変分法」という数学的な概念、技術があります。これに触れたのがこの頃だったので、関係があるような気もしますが、思い出せません。ずいぶん、昔のことなので。
偏微分方程式論は、偏微分方程式系という数学的対象の数学的構造を数学的に研究する学問です。一つ前の段落で触れたように、偏微分方程式そのものは、自然科学にも記述言語として用いられますから、よく混同されてしまいますが、数学としての偏微分方程式論というのは、記述言語としての正当性やその有用性を明確にしていく学問では、少なくとも元々は、ありません。偏微分方程式自体に内在されている構造や機能の探求を目指し、その概念の一般化、普遍化を行うものです。それは、人類の文化事業としての意味が大きく、壮大な体系をもつ一つのモニュメントになりうるものです。実際、日本人研究者の方々の中には、大きな貢献をされている方々が多数、いらっしゃいます。数学は、世界に向けて、日本人の業績を大いに誇って良い分野だと、真剣に思います。
しかしながら、「これに少しでも自分が関われるか?」という問いを自分自身に発したとき、「違うかな?」と思いました。能力的な問題ももちろんありますが、自分は、数学の記述言語としての面に興味があるだけだったのです。つまり、「応用」ですね。しかし、いわゆる「応用解析」は、その分野に入ってやってみるとなんだか中途半端なものでした。記述言語としての有用性や正当性は、解そのものがあるかどうかといったことの厳密な証明を行うことではなく、ユーザーである自然科学者からの評価で決まるべきです。なぜなら、有用かどうかは使ってみないと解らないからです。例えば、特殊関数(ベッセル関数やルジャンドル関数、エルミート関数といったもの)。これは有用でした。実際に物理学者をはじめとして、これら応用解析の成果の有用性を疑う人はいないでしょう。科学が細分化し、詳細化していく中で、こういった有用性から、「応用解析」としての評価を受けるべきなのは、コンピュータだと、ある時期、考えました。数学の記述言語としての有用性、正当性に興味があれば、コンピュータを利用するのは自然な成り行きです。そこで、これに真剣に取り組みました。思った通り、こいつは有用で、ナイスガイでした。
さて、ここまできて思うことがあるのです。やはり、自分は数学が好きだったんだということです。「縁」があったんですね。いろいろな立場から自分なりに自分の研究対象を一通り眺めてきましたが、数学の「芸」としての部分に最近は惹かれています。「芸」は、観客と芸人との間にある、ある種の緊張と緩和で成り立つものでしょう。数学の「芸」について、最近は理解が得られにくくなっているようで残念です。
「芸」というのは、それが存在することそのものにある種の意味があるものなのです。お正月にはいつもの倍、「回して」くれる方に「何の意味がある?」と聞くのは野暮というもの。自分自身の「芸」を振り返ると、「至芸」と呼ばれるようになるにはほど遠いし、才能も感じられませんが、自分なりの「芸」を磨いて、自分なりの達成感を味わいつつ、自分なりの興味の中に入り込んでいきたいと願う今日この頃です。もちろん、「芸」には、上でも述べたように、観客が必要なのですが、しかしながら、観客に媚びることが「芸」のためになるとは限らないといったこともあります。そこのところが芸人のセンスというものですし、良い観客が良い芸人を育てるし、その逆もまた真なのです。このような時代性の中ではなかなか至難かも知れませんけど。

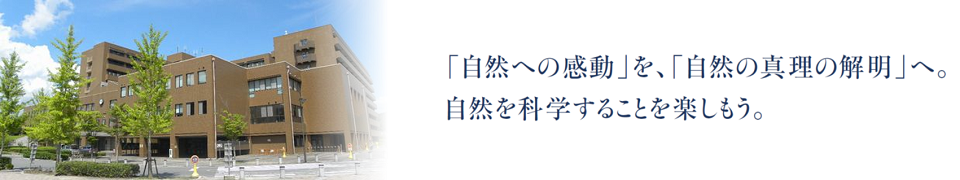
 Home
Home