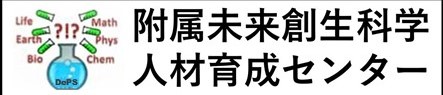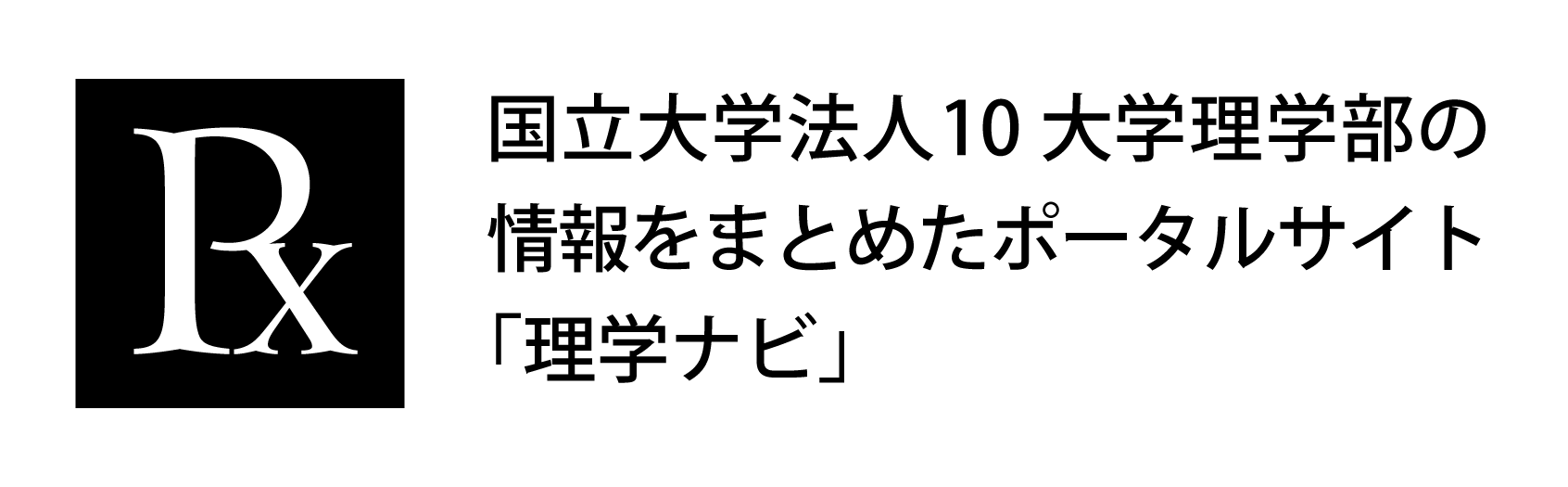私の研究者人生:月向 邦彦(数理分子生命理学専攻)
氏名:月向 邦彦
専攻:数理分子生命理学専攻
職階:教授
本研究科ホームページに連載「私の研究者人生」が始まり、トップバッターを仰せつかりました。定年を来春に控え、自分の研究者人生を振り返ってみたいと思います。多くの先生や共同研究者、学生達に助けられながら、オリジナリティーのある研究を目指して努力してきた日々でしたが、自分なりには結構ドラマチックな研究者人生であったと感じています。我々大学人にとって、研究だけでなく教育や大学運営、学会業務なども大事な仕事ですが、限られた紙面ですのでここでは省略させていただき、研究生活の光の部分にできるだけスポットを当てて紹介し(本当は同じくらい影の部分もあるのですが)、若い研究者、これから研究者の道を目指す学生諸君に少しでも励みになればと思います。
学生時代
私は本学理学部化学科で学び、卒論から修士課程を修了するまで3年間、物理化学講座(当時、山村等教授担当)でポリプロピレンの膨潤現象の研究に取り組みました。P.J. Flory(1974年ノーベル化学賞受賞)の著書で高分子溶液の格子モデルに魅せられ、固体から溶液まで高分子について幅広い勉強をしました。卒論では NMRを用いて、分子運動の活性化エネルギーに及ぼす結晶化度と膨潤の影響を調べ、先生に何度も直されながらも英語で書いた論文が広大理学部紀要に載ったときは感激しました。修士では蒸気圧測定装置を設計・製作し、蒸気吸着平衡の実験を行いました。装置が完成したのは修士4年の8月でしたので、それから修論提出まで大変でした。卒業式までに大急ぎで書いた論文が米国の雑誌に掲載されていますが、修士修了までに曲がりなりにも英語で論文を2報書けたことは、その後の私の研究人生にとって大きな自信になりました。今から思えば、研究者への準備期間として充実した学生時代だったと思いますが、英会話についてはもっと勉強しておくべきだったと後悔しています。
愛知教育大学時代 (1968−1971年)
修士修了とともに、1968年4月、愛知教育大学化学教室に助手として奉職しました。学生の身分から学生を指導する立場になり、不安と責任の重さを感じながらも、青雲の志をもって広島を後にしました。世はまさに学園紛争の最中でしたが、学位という大きな目標に向かって日夜頑張っていました。当時は、合成高分子の研究が成熟するにつれ、「天然物を見直そう」との機運が高まっていました。また、オリゴマーからポリマーへの転移領域の研究がブラックボックスとして残されていました。このような背景のもと、井上友治教授の指導により、天然多糖類であるデキストランの研究を始めました。臨床用デキストランを製造する際に生成する種々の分子量のオリゴマーを分画し、その水溶液の特性を詳細に調べたところ、重合度12以上で高分子的特性が現れることを見出し、学位論文としてまとめることができました。合成高分子から天然高分子への研究の転換は、有機溶媒から水溶液系への移行でもありました。
名古屋大学時代(1971−1995年)
名古屋大学農学部に食品工業化学科食品物理化学講座が新設され、公募で助手に採用されました。1971年6月のことです。愛知教育大学は私にとって楽しい職場だっただけに苦渋の選択でしたが、新しい研究分野を切り開けるのではないかと期待して思い切って移りました。食品の物性についてはまったく無知でしたが、食品の主要な構成成分は水であることから、野口肇教授とともに、生体高分子と水との相互作用を柱として熱力学的研究を展開することにしました。電離性多糖類と金属イオンの選択的結合能や水和の研究をゾル-ゲル転移などの相転移現象の理解へと拡張していきました。
しかし、食品の物性にとって蛋白質の安定性は重要な因子であり、蛋白質の溶媒和についての深い理解が必要です。そこで、この分野の第一人者である米国ブランダイス大学のTimasheff 教授に手紙を書き、留学をお願いしました。面識もなく、蛋白質についての研究業績もないので心配でしたが、A4タイプ用紙で3〜4枚のResearch Proposalを書かされ、それが採択になったときは非常に嬉しく思いました。こうして、1975年3月から2年間、妻と1歳の娘とともにボストン郊外のウォルサム市で留学生活を楽しむことになりました。といっても、最初の年は成果も出ずかなりのプレッシャーを感じました。実験で右手を負傷し、3ヶ月近く実験のできない日もありました。幸い、Biochemistryという雑誌にTimasheff教授と書いたグリセロールによる蛋白質の選択的溶媒和と安定化の機構に関する論文は700回近い引用を数え、一応、留学のノルマは果たせたのかなと思っています。留学は多糖類から蛋白質への研究の展開のきっかけとなり、私の研究者人生において大きな財産となりました。
留学から帰国してこれからというとき、野口教授が病で倒れ、1年余りの闘病の末他界という思いもかけないことに遭遇しました。助手という不安定な身分でしたので、生き残るために必死でした。科研費や各種財団からの助成を受けて何とか研究を続けることができました。幸い、それまでの研究が少しずつ認められ、 1980年にデキストランの研究がアメリカ化学会シンポジウム、蛋白質の圧縮率の研究がアメリカ熱測定会議の招待講演に選ばれ、1983年に、「生体高分子の水和現象に関する物理化学的研究」で日本農芸化学会奨励賞を受賞することができました。1985年助教授に昇任できたときは、やっと研究者としてやっていけそうかなと少し安堵するとともに、新たなチャレンジへの意欲が湧いてきました。
留学中にアイデアを暖め帰国してすぐ取り掛かった仕事に、蛋白質の圧縮率の研究があります。蛋白質溶液の超音波音速と密度を正確に測定することにより断熱圧縮率を決定しました。圧縮率が蛋白質の個性(分子内部の原子のパッキング状態)を敏感に反映することを 1979年の論文で明らかにしましたが、1986年にBiochemistryに発表した圧縮率と構造因子との相関の論文は、翌年のNatureの News and Views欄で紹介され、広く世界に知られることとなりました。圧縮率は高圧力下での蛋白質の挙動を理解するための基礎データとして重要ですが、体積の揺らぎを直接反映することから、その後の蛋白質の構造・揺らぎ・機能相関の研究に大きく発展させることができました。一方、1980年代中頃から世界的に高圧生物学やマリンバイオテクノロジーが一気に開花して、我が国では食品加工への高圧利用が盛んになってきました。私も留学前に購入していた光学窓付き高圧容器を用いて各種生体高分子のゾル-ゲル転移への温度・圧力効果を調べ、温度軸だけからでは分からなかったゲル化機構と水和の関係の一端を明らかにすることができました。このような基礎的研究を進めていたこともあり、1992年、豊橋に設立された「超音波・高圧食品加工技術研究会」の研究技術指導を 1998年まで担当することになりました。超音波発信器や高圧容器のメーカーに食品会社を含め17社の企業と、超音波振動子を組み込んだ高圧容器を開発し、食品加工への超音波と高圧の相乗効果の研究に取り組みました。残念ながらそのような食品を世に出すまでには至りませんでしたが、1993年に研究会のメンバーとともに執筆した特集記事「食品加工への超音波利用」が第5回超音波テクノ賞に選ばれました。基礎研究と応用開発研究の接点に触れることができ、私の研究者人生の中で貴重な体験でした。
助教授になって始めた仕事に、大腸菌ジヒドロ葉酸還元酵素のループ機能解析があります。1980年代初頭には遺伝子組み換えが蛋白質の研究手段として確立され、米国を中心に変異蛋白質に関する論文が目に付くようになりました。蛋白質のアミノ酸を部位特異的に自由に改変できることは、大きな驚きであり魅力でもありました。それまでの蛋白質の熱力学的研究をミクロな構造と結びつけたいと考え、40歳代半ばにして学生とともに大腸菌ジヒドロ葉酸還元酵素の部位特異的アミノ酸置換を始めました。当時は酵素の活性部位や疎水性コアでのアミノ酸置換の研究がほとんどでしたが、私は蛋白質の構造・揺らぎ・機能相関の解明にはフレキシブルループの役割を明確にする必要があると考え、ループ上でのアミノ酸置換を始めました。今でこそ遺伝子組み換えは日常的な実験となっていますが、当時は4種のDNA塩基を購入し自分でプライマーの合成からやらねばならない時代でしたので、一つの変異体を作成するのに大変時間を費やしました。それでも、最初の変異体G121Vが野生型の200分の1程度の活性しかなく、予想通り基質との親和性(Km)は変わらずターンオーバーの速度(kcat)が大きく影響を受けることがわかったときは興奮しました。変異体を増やしていく中で、フレキシブルループ上でのアミノ酸置換が、構造の揺らぎの改変をとおして機能にまで及んでいるとの確信を強く持つに至りました。
こうして名古屋大学で過ごした24年間は、様々な研究へのチャレンジとライフワークの構築を目指した時代でした。
広島大学時代(1995—2006年)
1995年、公募により広島大学理学部物性学科教授に採用され、27年ぶりに母校に帰ってきました。大学院は遺伝子科学独立専攻に所属していて、さらに重点化にともなって数理分子生命理学専攻に、学部は化学科へと目まぐるしく所属を変わりましたが、母校で最後の教鞭を取れることは望外の喜びでした。11年という短い教授生活で、どこまで研究を発展させ集大成できるか不安でしたが、蛋白質の構造・物性・機能を総合的に教育研究できる研究室作りを目指してきました。幸い、スタッフと学生に恵まれ、科研費も何とか継続的に採択され、これまでの研究を発展させることができました。糖やポリオールによる蛋白質安定化機構の研究は、熱容量レベルでの理解を目指してデータの蓄積ができました。ジヒドロ葉酸還元酵素の研究は、大腸菌だけでなく深海微生物由来の酵素にまで発展し、酵素の耐圧機構解明へ向けて進んでいます。蛋白質の圧縮率の研究は、1アミノ酸置換により圧縮率が大きく変化することを見出し、2000年には「蛋白質の構造・揺らぎ・機能相関の研究」で日本化学会学術賞を受賞することができました。この研究は、さらに質量分析による水素/重水素交換の実験へと展開しています。
広島大学で新しく始めた研究として、「放射光を利用した真空紫外円二色性分散計(VUVCD)の開発と生体分子構造解析への応用」があります。1997年に本学に放射光科学研究センターが設置され、谷口雅樹センター長からビームライン15を用いてVUVCD装置の開発を要請されました。それまで名古屋大学時代に13年間にわたって科研費(試験研究)で本装置の開発を申請し、不採択続きで諦めていたところに、理想的な放射光源を使ってこの装置を作れることになったのですから夢のような話でした。作る以上は世界のどこにもないものをとの意気込みで、日本分光株式会社と共同して設計にかかりました。光学系を全て真空下に置き、さらに光サーボリファレンスシステムを導入して装置の安定性を高め、2000年に世界ではじめて水溶液系で140nmまで測定可能な VUVCD装置の開発に成功しました。国際会議で何度も招待講演に選ばれ、これから大きな成果が期待できるところまでこれたのは、まさに学生諸君のたゆまない努力の賜物でした。
このように、私の研究は合成高分子に始まり、多糖類、蛋白質など生体高分子の物理化学的研究へと展開してきました。一見、まとまりのない研究展開に見えるかもしれませんが、常にオリジナリティーを求めて境界領域をさまよってきた結果でもあります。私が才能的に研究者に向いていたかどうか定かではありませんが、才能の足りない部分を何とか努力で補ってきた研究者人生でした。独自の発想で研究課題を設定し、それを実行して結果を自分で検証し、それを経験(情報)として、新しい法則・実験法や物質の発見・発明へと繋げる作業は、非常に創造性に満ちて楽しい仕事です。私がこれまで研究を続けてこれたのは、この魅力があったからかもしれません。大学は法人化を迎え、落ち着かない雰囲気にありますが、いつまでも学生とともに研究の喜びが味わえる大学であって欲しいと願っています。

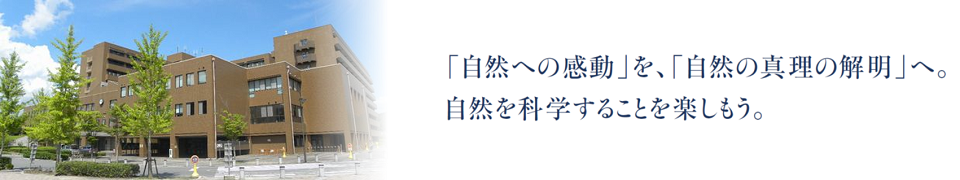
 Home
Home