当会の刊行物一覧

広島大学日本語作文コンクール事務局 編
2026年1月 刊行
本書は、記念すべき第1回目のインドネシアのコンクールにおいて厳正な審査の結果決定した上作品を集めた受賞作品集である。日本語を学ぶ学生をはじめとした多くの方々の元へ届き、日本語学習の励みとなる一冊である。

奥田 伸子,三時 眞貴子 編著
並河 葉子,山本 千映,磯野 将吾,大澤 広晃,森本 真美,竹内 敬子,江里口 拓 著
2025年12月 刊行
「自由な労働」は本当に自由だったのか? 奴隷、囚人、女性、子ども――、そして白人男性労働者。大英帝国を支えた「不自由な」労働者たちの声から、近代社会の光と影を暴き出す画期的な論集。
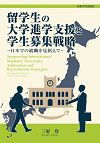
三好 登 著
2025年9月 刊行
留学生が日本の大学に進学するにあたって,どのような学生募集が望ましいのか,さらには大学卒業後,いかに日本社会で就労して定着しているのか,というテーマについて明らかにする。

有馬 卓也 著
2024年12月 刊行
中国古典を共通の教養として持つ維新志士たち(水戸志士・西郷隆盛・高杉晋作・雲井龍雄など)が詠んだ漢詩に表れた忠・孝・狂などの語を手がかりに、公文書では見えてこない彼らの想いを明らかにする。

弘兼 憲史 著
2024年10月 刊行
人類史上初の原爆投下によって前身校の多くが甚大な被害を受けながら、被爆から4年後の焦土に、「平和の大学」として誕生した広島大学。これを読めば、広島大学の魅力が分かる!

市川 浩 著
2024年11月 刊行
技術とは何か?―― この問いへの答えを探究した1930年代ソ連の論者たち。過酷な政治史の裏面に彼らの正体,背景,そして歴史の闇に消えたオルタナティヴを探る。

林 幸一 著
2024年1月 刊行
正規・非正規の雇用区分の基準について,諸外国におけるフリーランスなどの社会保険・労働条件などを中心に検討する。

三好 登 著
2023年11月 刊行
大学教育の学習成果について,コロナ前とコロナ禍の比較から検討する。

松田 充 著
2023年3月 刊行
「教授学」について,批判理論と授業研究という二つの視点から検討する。

富川 光 著
2023年2月 刊行
「ヨコエビ」というマイナーな、しかし面白い秘密に満ちあふれた生物について、数々の秘密を探る。

加藤 房雄 著
2023年2月 刊行
一次資料を駆使した年来の経済史研究の成果により、ドイツ世襲財産制の歴史的内実の多面的問題群を解き明かす。

盧 濤 著
2022年12月 刊行
現代の日本人学生の見方を把握することにより、日中異文化コミュニケーションの教育研究及び他の領域の交流に寄与する。日中対照。

下岡 友加, 柳瀬 善治 編
2022年3月 刊行
『台湾愛国婦人』は1908-1916年にかけて、〈帝国〉日本が〈外地〉で刊行した初の女性雑誌であった。小説、評論、短歌、映画、画報、童話、講談、漢詩、埋め草などから本雑誌の性格を照射する。

竹内 正興 著
2022年2月 刊行
充実した学生生活を送ることのできる環境を整えるため、大学入試を取り巻く構造と問題点を教育社会学的観点から示した上で、不本意入学者の現状を分析する。

片柳 真理, 坂本 一也, 清水 奈名子, 望月 康恵 著
2022年1月 刊行
紛争により被害を受けた個人の権利の救済に着目し、平和構築における国際法の役割や意義、さらに課題を論じる。

鈴木 理恵 著
2021年11月 刊行
咸宜園は,1817年に広瀬淡窓によって天領日田(現在の大分県日田市)に開かれた漢学塾である。本書では,咸宜園独自の教育システムが,同塾門人が開いた塾(系譜塾)を通して各地へと展開し,明治期にも継続した様相を描いている。

山﨑 勝義 著
2021年4月 刊行
物理化学の特定の事項についての疑問点を攻略するシリーズ。
著者自身が抱いた疑問や誤解の経験を明示し,解決目標を明確にした上で,著者がどのような“武器”を用いてどのように疑問を“攻略”したかという“体験談”を記した解説書。

山﨑 勝義 著
2021年4月 刊行
物理化学の特定の事項についての疑問点を攻略するシリーズ。
著者自身が抱いた疑問や誤解の経験を明示し,解決目標を明確にした上で,著者がどのような“武器”を用いてどのように疑問を“攻略”したかという“体験談”を記した解説書。

山﨑 勝義 著
2021年4月 刊行
物理化学の特定の事項についての疑問点を攻略するシリーズ。
著者自身が抱いた疑問や誤解の経験を明示し,解決目標を明確にした上で,著者がどのような“武器”を用いてどのように疑問を“攻略”したかという“体験談”を記した解説書。
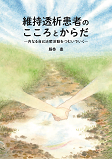
服巻 豊 著
2021年2月 刊行
慢性疾患(維持透析治療を受けている)患者が苦悩の状況にありながらも、自らを励まし、力づけ、自らを少しでも楽にしようとする「こころの内発的な自己治癒活動の存在」に注目する。

林 幸一 著
2020年8月 刊行
EUのVATにおける税の累積排除制度を中心に、比較法の視点からVAT制度について紹介・検討する。

宮川 朗子, 安川 孝, 市川 裕史 著
2019年9月 刊行
最近の研究動向と3点の楽しい論文に加え、フランス大衆小説を研究する上で読むべき参考文献と、フランスにおける大衆小説の歴史を見渡せる年表を巻末に収める。

寺垣内 政一 著
2019年3月 刊行
集合論の基本的な知識だけを用いて、ユークリッド幾何と非ユークリッド幾何を同時に構築する。

衛藤 吉則 著
2018年1月 刊行
西が中心に据える〈虚〉という概念に注目し、彼の思想を、戦前における東西の思想的蓄積と発展のうちに位置づけ直し、「平和・和解」理論としての可能性を問うた。第二部では、未整理であった広島大学所蔵の膨大な西晋一郎関連資料の目録をデータ化し収録した。

伊藤 敏安 著
2017年3月 刊行
地方分権一括法の施行、「平成の大合併」、「三位一体の改革」といった2000年以降の制度改革は、市町村財政にどう影響したのか ── 。
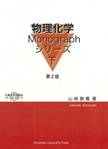
山﨑 勝義 著
2016年11月 第2版第1刷 刊行
新たに第25章「相律における成分の数」が追加された。相律の学習において初学者を悩ませることが多い「構成成分の数」と「成分の数」の相違を生み出す"制約"の根拠,および相律と平衡定数の関係を理解するための解説が記されている。

高橋 衛 著
2016年10月 刊行
本書は「大塚史学」と「宇野理論」を批判的に克服し、新たな経済理論の開発を目指すものである。内容は著者の自分史を交え平易にし、専門家から市民まで幅広い読者に親しみやすくなっている。

安村 誠司, 神谷 研二 編集
2016年8月 刊行
本書は、2014年1月に「原子力災害の公衆衛生 -福島からの発信-」として、日本語で出版された。このたび、広島大学の取り組みを加筆し、英訳版作が作成された。

松本 陽正 著
2016年3月 刊行
先行する習作との関係、形成過程研究、緻密なテキスト読解・分析による作品世界の提示、テマティックなアプローチ、比較文学的アプローチ等の多様な角度から『異邦人』を研究し、正確な読解を提出する。

於保 幸正, 海堀 正博, 平山 恭之 著
2015年10月 刊行
日本で暮らす上では避けては通れない土砂災害に対して、日常生活の中であらかじめ何を考え、何ができるのか、災害に備える上で示唆に富む一冊。

―広島大学理学部地球惑星システム学科へようこそ―
広島大学理学部地球惑星システム学科 編
2015年10月 刊行
太陽系と地球の形成、そして地球環境の変遷と生命の進化について、これまで分かってきたことだけでなく、これらを解明するためにどのような取り組みがなされているのかを紹介する。

木下 正俊 著
2015年4月 刊行
わが国の金融システム改革を金融の 効率化・高度化・融合化・安定化の観点から多面的に捉え、改革を実現する法的インフラ整備の取組みを検証した渾身の書。

木原 成一郎 編著
2014年11月 刊行
教師が体育の授業を改善しようとする時に求められる体育の目標と評価とはどのようなものか、授業研究の成果 に基づいて提案した本書は、体育授業で「指導と評価の一本化」を目指す教師必読の書である。

大塚 豊 訳
2014年3月 刊行
1931年、ドイツのベッカー、イギリスのトーニー、フランスのランジュバン、ポーランドのファルスキーからなる教育使節団が、国際連盟の知的協力国際委員会によって中国に派遣された。これら欧州の代表的賢人の目には、当時の中国教育がどう映ったか。

山﨑 勝義 著
2013年8月 第1版第1刷 刊行
物理化学の特定の事項についての疑問点を攻略するシリーズ。
著者自身が抱いた疑問や誤解の経験を示し、解決目標を明確にした上で、著者がどのような"武器"を用いてどのように疑問を"攻略"したかという"体験談"を記した解説書。

山﨑 勝義 著
2013年8月 第1版第1刷 刊行
物理化学の特定の事項についての疑問点を攻略するシリーズ。
著者自身が抱いた疑問や誤解の経験を示し、解決目標を明確にした上で、著者がどのような"武器"を用いてどのように疑問を"攻略"したかという"体験談"を記した解説書。

広島大学大学院文学研究科教務委員会 編
2013年3月 刊行
広島大学大学院文学研究科の教授たちが、これから文学部で学ぼう!文学部に進学したい!という人たちに向けて作成した1冊。

樋口 昌幸 著
2013年2月 刊行 (2009年 初版刊行)
広島大学出版会から2009年に発行し、絶版になっていたものを加筆して再版したもの。英語の歴史的変化から冠詞の本質的機能を究明する学術書。

―未病および生活習慣病から化粧品まで―
杉山 政則 著
2012年10月 刊行
乳酸醗酵の科学と食文化の歴史から、植物由来の乳酸菌「植物乳酸菌」の優れた保健機能性を解説し、病気の予防や未病の改善に向けた乳酸菌の活用戦略をわかりやすくまとめた一冊。

広島大学次世代エネルギープロジェクト研究センター 編
2012年3月 刊行
日常的に接しているテレビ・自動車などの省エネ技術などについて、複数の原理が効果的に組み合わされて1つの機器として機能している様子を説明。

牧 貴愛 著
2012年3月 刊行
教員の質的向上について、「専門職としての教員」、「教員に求められる資質・能力」、「教員に求められる倫理」といった観点からタイの改革内容を体系的に解明している。

―シェイクスピアとその前後の詩人たち―
吉中 孝志 著
2012年3月 刊行
著者自身や愛するひとの名前の痕跡を分析することによって、詩人たちの生きた時代や彼らの心を読み解こうとするユニークな作品。

広島大学原爆死没者慰霊行事委員会 編
2012年4月 刊行
広島の原爆被害を受けた大学としての使命感に基づき、現場の資料による被害状況や社会的対応についてまとめた学術報告集。

藤越 康祝, 若木 宏文, 栁原 宏和 著
2011年3月 刊行
確率と統計の基礎理論を数学的に解説した教科書。また、回帰分析法の主要な方法、統計的モデルの選択問題、計算機統計手法、統計ソフトRによるデータ要約などの今日的な情報も豊富に含む。

広島大学図書館 編集/町 博光 監修
2011年3月 刊行
方言研究の泰斗、広島大学名誉教授藤原与一博士が遺した研究資料の目録。全国各地域の方言資料、録音資料・方言採取カード、博士の著作類で構成されている。

―背景の社会学的検討―
李 敏 著
2011年3月 刊行
はたして中国の高等教育の大衆化は、大卒者の就職難を引き起こした「元凶」なのか。緻密なデータ分析に基づき、中国の高等教育及び大卒者の就職の実態を探る。
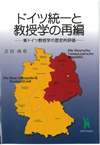
―東ドイツ教授学の歴史的評価―
吉田 成章 著
2011年3月 刊行
ドイツ統一によって教授学がどのように再編されるかを、東ドイツ教授学の歴史的評価を中心として検討する。

―マイノリティから見たドイツ現代史 1893-1951―
長田 浩彰 著
2010年3月 刊行
ユダヤ教徒とキリスト教に改宗した人々を「ユダヤ系ドイツ人」という共通概念で捉え、1893-1951年のドイツ史をマイノリティ側から描く意欲作である。

小谷 朋弘 著
2010年3月 刊行
離婚紛争の発生からその処理、さらには処理を支える社会的支援システムまでをも視野に入れて、離婚における男女格差の問題を検証する。

八尾 隆生 著
2009年3月 刊行
小農経営が社会の趨勢となっているヴェトナム北部デルタとは著しく異なった「丘陵の民」が現ハノイに新王朝=黎朝を建て、デルタ出身者と対立と分業・妥協しながら、「安定した小農社会の世紀」をもたらしたことを、新出史料をもとに論じる。

布川 弘 著
2009年3月 刊行
近世後期から1920年代に至る日本社会を研究対象として,日本的近代家族の形成過程を考察した作品。イエの観念を支えにして営まれてきた家族と国家・社会との歴史的結びつきを示した事例を踏まえて,様々な角度から分析する。
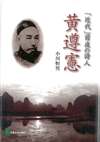
小川 恒男 著
2008年3月 刊行
清末の詩人である黄遵憲の作品を,言語表現の側面から実証的に分析し,彼の世界観や文学観について論じる。
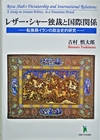
―転換期イランの政治史的研究―
吉村 慎太郎 著
2007年10月 刊行
パフラヴィー王朝初代国王レザー・シャーが支配した戦間期イランの内政と国際関係を検討した学術専門書。

広島大学五十年史編集委員会, 広島大学文書館 編
2007年9月 刊行
新制広島大学の発足から創立50周年までの歴史を対象とする。必要に応じて本学前身の旧制諸学校の沿革および50周年以降の歴史についても記述する。
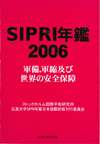
広島大学SIPRI年鑑日本語翻訳版刊行委員会 訳・編
2007年3月 刊行
今日における国際紛争,軍縮,安全保障の主要な問題に対する情報収集力と分析力で高く評価されている「SIPRI年鑑」待望の日本語翻訳版。

前野 弘志 著
2007年3月 刊行
碑文を文字史料としてのみならず,碑の形,大きさ,建立場所等の非文字情報にも着目して,アッティカという地域において碑文文化の諸相を明らかにした。

市橋 勝 著
2007年3月 刊行
日本経済の長期的特質を「多部門の構造変化」と「マクロの長期的推移」の観点から分析した画期的な著作。また,90年代の位置付けや特徴を明らかにし,長期不況の原因を分析した。

井内 太郎 著
2006年3月 刊行
16世紀イングランドの国家財政構造の特質を分析しながら,それがなぜ17世紀半ばの内乱期に破綻してしまうのかを明らかにし,18世紀型の国家財政成立に向けて残された財政的課題を検討する意欲的な作品。
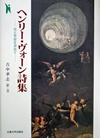
吉中 孝志 訳・注
2006年3月 刊行
初期近代英国形而上派詩人の一人,ウェールズの神秘主義者,光の詩人,ヘンリー・ヴォーンの代表的詩群の本邦初訳。

原野 昇 著
2005年3月 刊行
フランス中世の各時代にわたる中世文学の代表的な作品を具体的に取り上げる。

 Home
Home