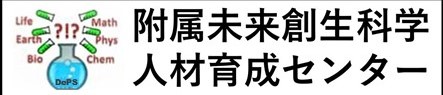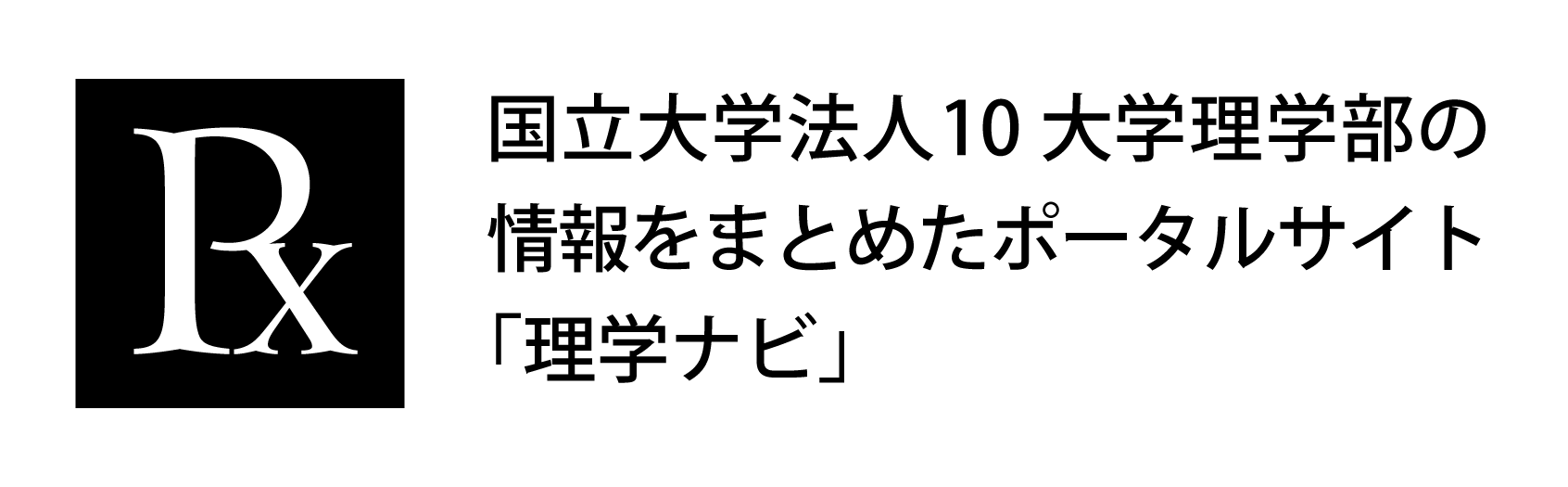振り返ると、そこには…
氏名:森下 文浩
専攻:生物科学専攻
職階:助教
専門分野:動物生理化学
略歴:1960年生まれ 1983年3月 広島大学理学部生物学科動物学専攻 卒業 1985年3月 広島大学理学研究科博士課程前期動物学専攻 修了 1988年7月 広島大学理学研究科博士課程後期動物学専攻 単位修得退学 1988年8月 広島大学理学部助手 1989年9月 理学博士(広島大学) 1995年8月より96年6月まで、ヨーク大学 客員研究員(文部省在外研究員) 2004年4月 独立行政法人国立環境研究所 客員研究員 2005年4月 広島大学理学部 学部内講師
齢四十の半ばを過ぎて我が身を振り返るとき、なぜ今、研究者なのか、その明確な動機を語ることは難しい。確かに少年時代は虫取りが好きで生き物に親しみを感じていたが、それはそのころの男の子としては普通のことだったと思う。学問としての生物学に興味を持ったのは、中学校・高校で受けた生物の授業の影響であろう。特に、高校生時代にお世話になった故白神澄二先生の影響は大きかった。ただし、そのとき志したのは「生物の先生」であって、研究者というわけではなかった。ところが大学受験の直前、やむを得ない事情で理学部を受験することになった。結果的にはそのとき研究者になることが半ば決まっていたのかも知れない。幸いにも、共通一次試験の第一期生として本学理学部生物学科動物学専攻に入学することができ、2年生後期からの2年半は被爆建物である旧理学部1号館で過ごした。
卒論配属を決めるにあたり、動物生理学教室(当時)の山田耕司教授の指導を受けることとなった。卒論研究を終えた時、そのまま大学院へ進むことは自分の中では自然な流れであったように思う。修士課程(博士課程前期)はともかく、博士課程後期にまでよく行かせてくれたものだと、両親には(心の中で)感謝している。そのころの研究内容は、メダカの体表にある色素胞を材料にして細胞内色素顆粒の運動を調節する神経機構を調べる、というものであった。メダカの鱗には、メラニン顆粒を持つ黒色素胞がある。メラニン顆粒が黒色素胞内に均質に拡散すると体色は暗化するが、黒色素胞を支配する交感神経が興奮すると色素顆粒は細胞中心部に凝集し、体色は明化する。このとき交感神経から神経伝達物質としてノルアドレナリンが放出され、黒色素胞の表面にあるアドレナリン性α受容体を刺激する。その当時、ほ乳類のα受容体に、α1,α2というサブタイプがあり、それぞれ薬物感受性や細胞内情報伝達機構が異なることが知られていた。私はメダカ黒色素胞のα受容体がα2タイプであることを薬理学的に示した。残念ながらそのとき既にスウェーデンの研究者が別種の魚で同様のことを報告していたのだが、彼らの考え方は色素胞の研究者の間にはあまり受け入れられていなかった。われわれの報告は、その考え方が定着することに多少なりとも貢献したと自負している。
その後、助手となった私にとって大きな転換点といえるのは、文部省在外研究員(若手)として1995年8月から10ヶ月間、カナダのトロント市郊外にあるヨーク大学で過ごしたことであろう。応募するにあたり、そのころ教授に昇進されていた松島治氏からヨーク大学のSaleuddin教授を紹介された。ところがSaleuddin教授の専門は色素胞とは縁もゆかりもない軟体動物の内分泌学である。松島先生は元々軟体動物の浸透圧調節機構を研究されてきて、その後、軟体動物・環形動物といった無脊椎動物の神経ペプチド(ペプチド性の神経情報伝達因子)に関する研究を行っていた。同じ研究室の助手としては、色素胞の研究を続けるよりここらで研究内容を軟体動物に乗り換える方が研究の展開が望めるかも知れない。思い切ってSaleuddin研へ行くことにした。Saleuddin研では、Helisomaという淡水産巻き貝を用いて研究を行うことになった。Helisomaはアルブミン腺という外分泌腺から様々なタンパク質を分泌して卵塊を形成する。そのアルブミン腺のタンパク質分泌活性にcAMPという細胞内情報伝達物質が深く関与することを確かめることができた。私にとってはゼロからの研究であったが、帰国直前には北米大陸最東端のニューファンドランド島で開催されたカナダ動物学会で発表することができた(おかげで本物の氷山を見ることができたのだが)。なにより、滞在中に多くの貴重な友人と下手な英語でも外国人とコミュニケーションを取ることは可能であるという自信を得たことが後の私にとって大きな財産となった。
帰国後は、松島教授、助教授として赴任した古川康雄氏(現総合科学部教授)らとともに軟体動物アメフラシの神経ペプチド探索に従事し、いくつかの新奇ペプチドを同定することができた。(世間にはヒトやほ乳類を対象にした研究でなければ役に立たない、と考える向きもあるが、アメフラシはその神経系の特徴から現代神経科学の基礎研究に不可欠なモデル動物である。そのことは、アメフラシを用いて記憶・学習のメカニズムを解明した米国のE. Kandel教授がノーベル医学生理学賞を共同受賞したことが証明している)。アミノ酸の数にして数個から十数個の小さなペプチド達であるが、誰も知らなかった新しい神経ペプチドを同定して世に送り出すことはそれなりに達成感がある。また、こうした研究は新しい出会いを生み出すものである。九州大学の下東康幸教授のおかげでわれわれが同定した神経ペプチドの立体構造を明らかにすることができた。また、国立環境研究所の堀口敏宏研究官と共同で、軟体動物イボニシを材料に、有機スズが神経機能に及ぼす影響を明らかにすることを目指して研究を展開することとなった。そして松島・古川両氏が転出された今、道端齋教授、植木龍也助教授とともに教育・研究に従事することとなった。
こうして振り返ってみると、様々な人との出会いが転機となって今の私に至っている。どうも私は性格的に「果報は寝て待て」タイプなのだが、それでも容赦なく(?)転機はやってきた。幸いにも「転落」となった転機はまだない。さて、次はどんな展開があるのだろうか。

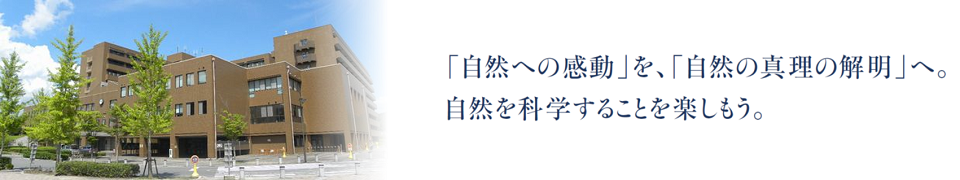
 Home
Home