研究井戸端トーク#6『共生・共創する社会を目指して』を開催しました
<日時> 2022年 8月 5日(金) 16:30~18:00
<場所> 広島大学ミライクリエ1F多目的スペース&オンライン(Zoom)ハイブリッド開催
<参加者> 延べ57名(大学教職員、大学院生、企業など)
<プログラム>
話題提供者からの短い話題提供後、自由な対話
司会:
関 恒樹 教授(広島大学 大学院人間社会科学研究科 / 文化人類学・東南アジア地域研究)
話題提供者:
山田 俊弘 教授(広島大学大学院統合生命科学研究科 / 生物多様性・生態学)
河本 尚枝 准教授(広島大学大学院人間社会科学研究科 / 社会福祉学)
吉田 真理子 助教(広島大学大学院人間社会科学研究科 / 文化人類学、環境人類学)
<主催>広島大学 未来共創科学研究本部 研究戦略推進部門(研究井戸端トーク担当)
第6回となる研究井戸端トークは、国際平和共生プログラムに属する関恒樹先生による司会のもと、前回に続き会場とオンラインとのハイブリッドでの開催となりました。話題提供者は、意識しなくても生物多様性を守れる世界に向けた仕組みづくりを模索している山田俊弘先生、日本に暮らす外国籍および外国にルーツをもつ日本人の福祉を調査している河本尚枝先生、文化人類学の立場から人と人以外の共生とは何かという研究を行っている吉田真理子先生。三者三様の視点から「共生・共創」をキーワードとする話題が提供され、自由なディスカッションも大いに盛り上がりました。部分的ではありますが、その内容をお伝えします。

登壇者の先生方

会場の様子
山田俊弘教授からの話題提供
アブラヤシ園に地域住民と緑の回廊を「共創」し、多様な生物との「共生」を
マレーシアやインドネシアの熱帯林を舞台に、生物多様性に関する生態学の研究を行っているという山田先生。広大なアブラヤシ園が広がるインドネシアとマレーシアは、食用油として世界で最も使われているアブラヤシの油、パーム油のシェア85%を占めています。日本では、サラダ油に使われる菜種油に続いて消費されているのが、加工食品などに使われるパーム油です。食用油の価格は、ここ数十年にわたり上がっていて、アブラヤシは“儲かる作物”。アブラヤシ園の拡大を食い止めるのは難しい状態に。しかし農園を広げるために熱帯雨林を切り拓いてしまうのは、オランウータンなど生息する動物にとっては大問題であり、「多様な生物との共生を共創することが必要」だと山田先生は語ります。
先生が研究対象としているエリアでは、アブラヤシ園が熱帯雨林を隔ててしまっていて、野生動物の行き来ができない状況です。そこを自由に動けるような緑の回廊をつくったほうがいいだろうと、山田先生の研究グループでは、広島の建設機械メーカーである「コベルコ建機」の協力を得て、広島大学の学生と、現地の学生や小学生が一緒になって植林を行っています。
保坂哲朗准教授がスーパーバイザーをされている先進理工系科学研究科の博士候補生、Ashrafさんの研究によれば、アブラヤシ園の中にカカオやバナナなど、アブラヤシでない作物を植えることで、相乗効果が期待できるとのこと。食糧の確保に加え土壌を豊かにすることにもつながり、環境にも農業経営にもいいWin-Winをつくれるのではないかと調査が進められています。
熱帯雨林の荒廃は数十年前から問題となっています。一度切り拓かれた森林が表土を失うと、森林の回復には途方もない時間が必要となる。実際、数十年前に切り拓かれ、かつ土を失った場所には、今もシダが生え、森は戻ってきていません。拡大に続くアブラヤシ園も、農業をしている間は肥料を投入し、豊かな農業環境をつくっていますが、ひとたび産業として成り立たなくなってしまったら、どれだけ荒廃地が広がることでしょう。「そういった懸念を常に抱いている」と山田先生は問題提起しました。
河本尚枝准教授からの話題提供
「多文化共生」は、多数派と少数派が意見を交わしながらの「共創」からなる
次に登壇した河本先生は、日本で暮らす外国がルーツの人たち、海外で暮らす日本人移民にフォーカスしながら、子供の教育や学習、高齢期の介護や福祉の支援ニーズについて研究しています。病気や障害、家庭環境や老化、貧困や孤独など、あらゆるリスクを乗り越えながら、私たち人間は生きています。それらは一人では乗り越えられない場合も多く、さまざまな支援が必要です。河本先生は、自身の研究テーマを、今の制度やサービスで不足しているものはないのかを考え、「その人らしい暮らし」の実現を目指すことだと説明します。
1970年代頃の日本では、マイノリティの運動として「多民族共生」という言葉がスローガンとして使われていました。当時の日本は、外国にルーツをもつ人たちの約95%が旧植民地出身者。「多民族共生」という言葉は、彼らが権利の獲得や、指紋押捺制度などの撤廃を求める運動のなかで、マイノリティ側が使い始めたものだそうです。一方、90年代になると、今度はマジョリティ側が「多文化共生」という言葉を使い始め、今では行政用語として使用されるまでになっています。2006年に総務省が出した「多文化共生の推進に関する研究会」の報告書で、「多文化共生」は「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義づけられました。しかし、いかにして共生を実現するのかは、法律もなく、現在進行形の課題になっていると、河本先生は指摘します。
子供の教育、就労、家族を呼び寄せる家族再結合、育児、医療、高齢期の問題など、人生全般に関わることが「多文化共生」の課題となっていますが、これらを解決し「多文化共生」を実現するためには何が必要なのでしょう。さまざまな研究がなされるなか、「共通して言われているのは、継続的に対話とコミュニケーションを続けていくこと」だと河本先生。かつては多数派側に少数派側が合わせていかなければいけない社会でしたが、今は差異を認め合いながら、その違いを受け入れて対等・平等な関係をつくる社会が目指されています。「多文化共生」は、何らかの政策をつくったから実現されるものではなく、その社会にいる多数派と少数派が意見を交わしながら共につくり上げていく…そんな「共創」からなる「共生」ではないかと、話題提供は締めくくられました。
吉田真理子 助教からの話題提供
牡蠣の世界を通して「共創」を考察。「共生」は必ずしも調和的な状態ではない
牡蠣のサプライチェーンにおける課題を、文化人類学の視点から研究している吉田真理子先生。まずスライドに映されたのは、ニューヨークのオイスターバーで出されている生牡蠣の写真です。一口に牡蠣と言っても、イワガキやポルトガルガキ、アトランティックオイスターなどさまざまですが、こちらはマガキ。日本が原産とされていて、ニューヨークでは「ロイヤルミヤギ」という名前で商品化されています。しかし日本のマガキとは形状だけでなく風味も違うとのこと。同じ種であっても、育てられている海域や生態系、養殖技術によって多様に変化し、牡蠣の付着物も産地によって全く異なるのだといいます。
世界中で商品化されているマガキは、いろいろなリスクを抱え込んでいます。最近では、海洋の酸性化により幼生の殻が形成されなかったり、海水温の上昇により適正な時期に産卵ができなかったりと、環境の変化からさまざま問題が発生。マガキにしか感染しないウイルスも出てきています。また、日本の生産地では、少子高齢化により漁協従事者が減少しており、加熱用のむき牡蠣の殻をむく“むき子”も減ってきていると吉田先生は説明します。こういった事態を受け、生産の現場と消費の現場も変容してきています。たとえばマガキにしか感染しないウイルスが出てきたことで、タスマニアの養殖業者たちは自然の海ではなく、屋内で種牡蠣から育成することをはじめました。また、牡蠣のトレンドも、むき牡蠣から殻つき牡蠣へとシフトしてきています。

吉田先生の関連著書
環境の変化から問題が発生するのを防ぐには、環境を浄化すればいい、というわけでもありません。たとえば瀬戸内海域では、戦後開発による高度経済成長を経て赤潮が頻繁に発生するようになりました。それによって牡蠣などが育たなくなったため、下水処理場の浄化機能を強化したところ、生活排水からの養分も除去されたことで、牡蠣にとって好ましくない貧しい海洋環境となってしまいました。そこで広島の地御前漁協は、鉄製の耕うん機で海底を掘り起こし、栄養塩を撹拌させる「海底耕耘」に取り組んでいるのだそうです。さまざまな状況が絡み合い、多様化している牡蠣の世界。「日和見的だったり競合的だったりするのが共生。必ずしもハーモニアスな状態ではない」。そんな吉田先生の言葉が印象的でした。
自由なディスカッション
研究者自身がアクターの一人として、共生・共創のプロセスに関わらざるを得ない
何かを共創するために研究者が介入した場合、その介入先からの反響をどう受け止めるのかは重要なこと。その点をどう捉えているのかという質問から、自由なディスカッションはスタートしました。
生物多様性を守る取り組みでは、「地域住民の合意を得ることが重要」だと山田先生。農民にとって、野生動物が農地に入ってくることは不安材料にもなりかねません。それに対し、緑の回廊をつくることで、ネズミなどのアブラヤシの害獣のプレデター(捕食者)であるメンフクロウなどが居ついてくれれば、最終的にはアブラヤシの生産力が上がり、生物多様性を守ることにもつながります。こういった意図を説明し、地域の人たちの理解を得られたことで、一緒に活動できることになったといいます。
河本先生が携わる社会福祉の分野では、関連制度をマジョリティの側がつくり、マイノリティの側が参与することも声をあげることも難しいのが現実です。そういったなか、より良い形を模索するために、他の専門職にも入ってもらう取り組みをしており、河本先生自身もアクション・リサーチとして関わっているのだといいます。たとえば戦前戦中に満州で生まれ、中高年になってから帰国された中国残留孤児の方は、日本語も日本の文化もわからないまま介護ニーズを抱える場合があります。しかしその存在に現場の人たちだけでは、なかなか気づけないことも。そこへ研究者や他の専門職が入り筋道をつくることで、制度やサービスをより良く変えていくことにもつながるというわけです。
河本先生の話を受けて、「私の分野は文化人類学なので、方法論にもつながってくる」と吉田先生。自身が調査対象である集団に加わり、長期にわたって観察する参与観察を通じて、生産地から消費地まで商品化に関わる人たちと知り合ったことで、市場関係者と生産者のマッチングに協力したこともあるといいます。一方、広島の海底耕うんの事業では、「文化人類学者が調査に加わることに漁協の方が疑問をもたれるため、その立場性を都度きちんと話すことが研究倫理として大切」だと話しました。
3人の意見に対し、「研究者自身がいろんなアクターの一人として共生・共創のプロセスに関わらざるを得ない立場である」と関先生。人の介入が、森林伐採のようにネガティブに働いてしまうこともあれば、緑の回廊や海底耕うんのように求められる場合もあります。「もはや手つかずの自然がないなかで、ある程度、人間の手を加えなければ望ましい状況がつくりだせなくなっている」という吉田先生の指摘に、共生・共創の重みを再認識しました。
共生する社会をつくるには、私たち一人ひとりの認知を変えることが必要
共生・共創する社会を目指すためには、学校教育も重要なカギを握ります。日本の学校では、子供たちに共生・共創をどれぐらい考えさせているのか。共生・共創を目指すにはどのような学校教育が理想・必要なのか。参加者から教育に関する疑問が投げかけられました。
それに対し、「教育学が専門ではないので全体的なことはわからないが」という前提で河本先生が、小中学校では「異文化理解教育」として授業が行われてきたと紹介。外国人の子供や外国にルーツを持つ子供が多い地域では、自分の学校にいる子供たちの国について知ろうとする教育例もあるのだといいます。必要な教育については、「肌の色が同じだからといって、日本語が通じる前提でカリキュラムをつくることから考え直した方がいい」と意見しました。
教育というテーマを受けて吉田先生は、「研究における共生や多様性も考えてもらいたい」と発言。たとえば新型コロナウイルス感染症のインパクトが、人種や社会階層によっても不均衡なものだったように、感染症の問題であっても医療以外とも複雑に絡み合っています。「自分の問題意識に照らし合わせて研究を行う場合も、専門分野だけではなく隣接領域にある研究や専門家と話して練り上げていく作業が必要。学際性が研究そのものの共生・共創につながっていくのでは」と提言。それを受けて、「共生する社会をつくるには、子供たちだけじゃなく私たち一人ひとりの認知を変えることが必要」だと山田先生。自然と人は分けて存在しているというかつての認知が今でもはびこっていますが、自分のいない自然、地球はあり得ません。「自分のアクトによって自分も変わるし地球も変わる。それを認知することで、自分はこの地球にどういった貢献ができて、どういった社会に変えたいのかという自覚が芽生えるのではないかと期待したくなった」と希望を語りました。
「共存」ではなく「共生」を目指すのであれば、その過程での対立は避けられない
共生について、「必ずしもハーモニアスな状態ではない」と語っていた吉田先生。その強い表現を受けて、共生の定義が問われました。
「研究を通じて見えてくるのは、寄生関係になる場合もあるということ」だと吉田先生。たとえば、マガキのみに感染するカキヘルペスウイルスや、牡蠣が貯蔵庫となり人間の小腸のみで増殖するノロウイルスなどはWin-Winの関係ではありません。「それぞれの種が依存し合ったり絡まったりしながら、共生という状態が常に安定的に保たれるわけではない。何かあったときに共生的なネットワークが崩れてしまうこともある。そういった意味では緊張関係をはらんでいる言葉だと理解している」と述べました。
さらに山田先生が、「社会での共生はWin-Winを思い浮かべるが、生物ではそれを指しているわけではない」と補足。二つの種がWin-Winになる相利共生だけでなく、どちらか一方だけがプラスになる片利共生、どちらか一方だけがマイナスの影響を受けてしまう片害共生、どちらかはプラスでも残りがマイナスになる、寄生や感染症に代表される敵対関係など、さまざまな形の共生があるといいます。感染症は宿種を殺してしまうこともありますが、ホストがいなくなることは病原体にとっても得ではありません。「そのため強毒性の病原体が短時間で弱毒性に置き変わっていくことが、さまざまな種で確認されている」と山田先生は解説します。
片や人を対象とする河本先生は、「さまざまな人が暮らす社会では、コンフリクトが生じないのが理想の形。ただ、ハーモニアスな状態をつくる過程で合意形成を目指せば、もちろん対立は生じるし、関係の悪化、争いにもなりかねない。できるだけ多くの人が納得しうる点を見つけていくのが、人と人、グループ同士、社会のなかでの共生になるかと思う」と回答。ただ単に対立を避けた没交渉では、共存にはなっても共生としては成立しないと強調。一言に「共生」といっても、さまざまな形があることを示してくれました。
研究井戸端トークを終えて
違うものが共生するがゆえに出てくる、リスクや不確実性に目を向けることも重要
関 恒樹 教授
単に異なるものが共に生きる、共にあるということだけではなく、何をつくりだしていくのか。人間が制度や文化をつくるのではなく、異なるものと対峙するなかで思いもよらなかったことが生み出されていくのも共創です。今回の研究井戸端トークを通じて、共生と共創の違いのようなものに注目していくことも必要だと感じました。決して調和や均衡だけではない共生。マイノリティとマジョリティであるとか、あるいは人と人ならざるものであるとか、それぞれ違うものが共生するがゆえに出てくる、リスクや不確実性に目を向けることも重要ではないでしょうか。

参加者の皆さんと記念撮影
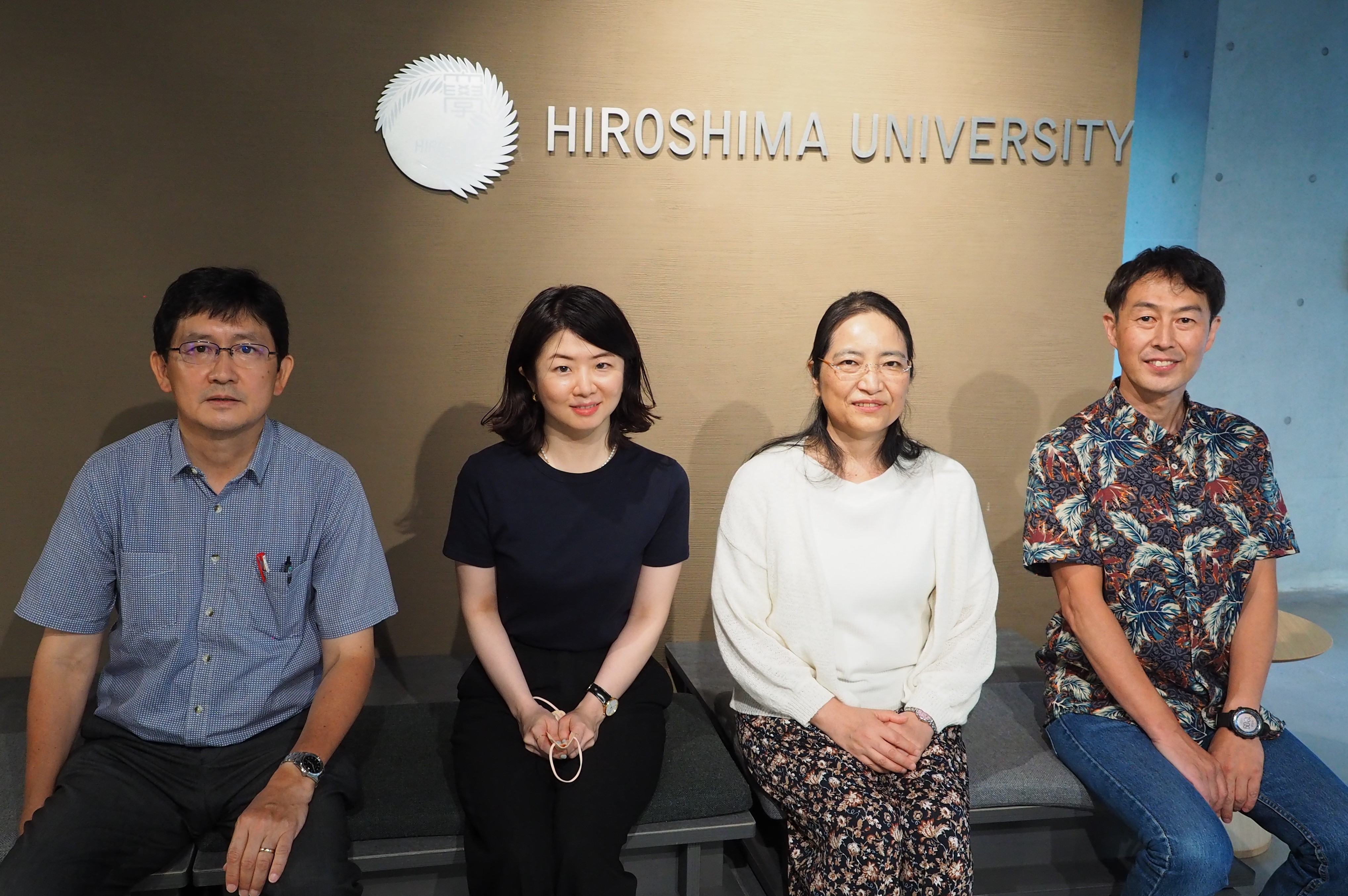
お疲れ様でした!
【お問い合わせ先】
未来共創科学研究本部 研究戦略推進部門
研究井戸端トーク担当
ura■office.hiroshima-u.ac.jp (■を@に変更してください)


 Home
Home


