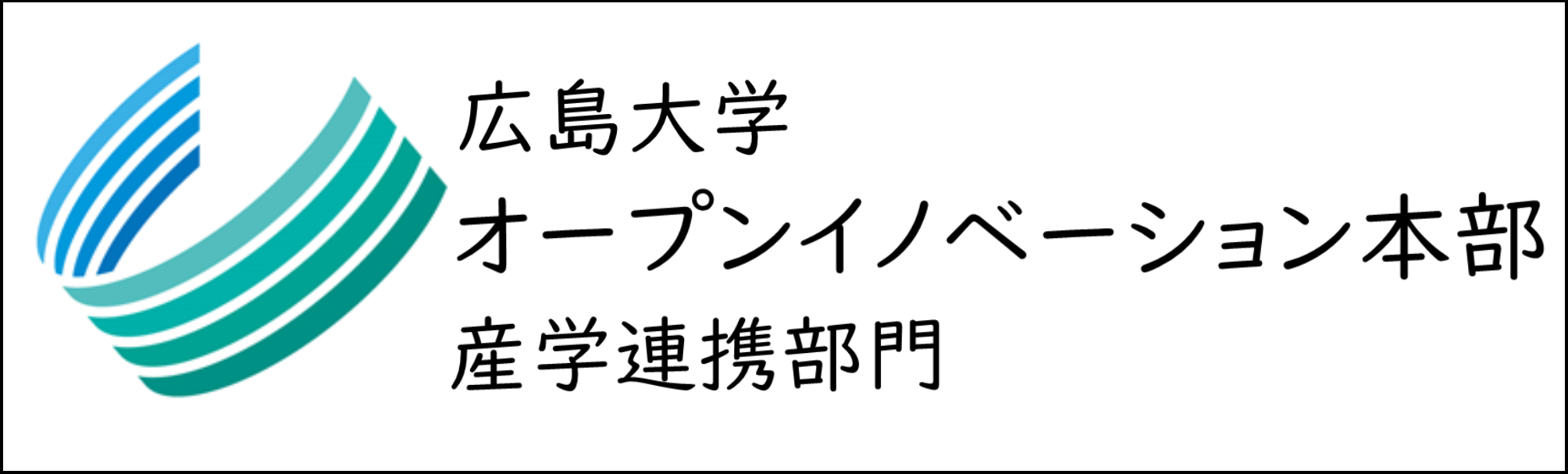第4回イノベーティブ企業家開催記
平成23年7月 三枝省三
開催日:7/11(月)18:00-19:30
講演者:株式会社 シギヤ精機製作所 相談役 鴫谷定昌 (しぎたにさだまさ)
演題:「もの作りの原点を求めて-100 年を活きる技つくり-
概要: 機械造りの職住一体の環境で育った演者は、高校生のときから今に至るまで,機械づくりに「一路精進」しました。かれは趣味にもして、技術をつなぐために小型SL 機関車も作り技術の作りこみと継承を真剣に取り組んできました。新しいだけがベンチャーでないことを示して頂きました。年輪を重ね,苦労と楽しみもまた重ね,新しさと古さを融合させました。会社を作った後の継続ある活動を,世代から世代へ受け継いだものづくりの原点を見せて頂きました。
開催記
予定の1時間前に準備室としている新産業創出・教育部門VBLオフィスに来ていただきました。演者の鴫谷(しぎたに)相談役は、大学で講演するのは初めてで、少し緊張気味でしたが、同行の奥さんともども楽しい準備時間とすることができました。
予告通り、2011年は創業してから100年目になり、その記念行事を終えた直後でしたので、会社の沿革を報告して頂きました。100年の歴史は山あり、谷ありの連続で、それらをコンパクトにかつ迫力を持ってのお話しでした。終戦直前の巨額の富と終戦後の家屋焼失と極貧からの再建、そして1960年に法人格となると同時に社長就任しました。 今でこそ、普通に行われている月給制と社員持ち株制度を即座に取り入れ、従業員に優しい会社にであろうと努力を重ねています。経営理念の、「よい環境、よい製品、よい人生」にはそのことへの強い思いを込めていました。
当時の従業員は約120名、2011年3月現在252名で、50年間で約2倍となっています。というより、なぜこの優良企業がこれだけの人員で推移しているかが疑問となります。それを相談役は、「そういう方針にしましたから」と、あっさりとした回答してくれました。巨大化ではなく、あえて高い質を維持するために適正規模を選択してきたのです。日本の「ものつくり」を基本から、そして工作機械のマザーマシンつくりに究極を求めたための経営方針なのです。企業経営に対する強いく高い意志を感じた次第です。マザーマシンはそれから子供のマシンを作りますので、精度の最高峰を極める必要があります。その基本が「キサゲ」作業です。機械には出来ません、ひとにしか出来ません。改善に改善を繰り返し、技を若者が身につけ、この技を次代の若者につなげていく、この継承を経て初めてできる技の世界です。
事業を着実に成長させていくため、生み出す工作機械は円筒研削盤を中心とし、研削技術の作りこみに特化しています。現在の健全経営もそれらの成果と強調していました。昨年度は間口が狭く画期的な省スペースの立て形円筒研削盤が十大製品に選ばれました。100年経ってなお元気をもっています。この元気を維持することがどれだけ難しいのか。多くの老企業・巨大企業の軌跡をみればその困難さが解ると思います。
講演はビデオを駆使し、口頭説明と動画による臨場感を取り混ぜたプレゼンでした。NHK、RCCなど多くの注目を集めている企業であることがわかります。特に円高のなかで、どうやってそれを乗り切るかが大きなテーマでした。海外移転、リストラなど直ぐに思いつく手段ではありますが、鴫谷相談役はきっぱりこれらを否定し、人員整理も海外移転もしないとはっきり宣言しました。(海外展開は当然継続します。)日本でなければ作れない強みをきちんと意識し、それを強調することで挑戦的にかつ着実にという経営思想をここでも明示して頂いた次第です。
講演が終了し、VBLオフィスに戻って来たのが、8時です。30分程度の質疑応答をお願いしておりました。参加の学生は8名でした。そこでは、シギヤという会社というよりは、鴫谷相談役(元社長)の経営方針や生き方に質問が集中しました。合理的な経営とは、車社会の変化に対する見解とか、趣味の伸ばし方とか。
お年を召した方には忙しい4時間ではなかったかと思いますが、元気に帰って行かれました。ますますの健康をお祈りしつつ、感謝とお礼の気持ちを込めて、本報告を終えます。
開催後記
本年度はこれでイノベーティブ企業家を終了します。皆さんの多大な応援に感謝申し上げます。本年度はものつくりイノベーションでしたが、来年度はサービスに関するイノベーションの企画を考えています。来年度もご期待下さい。
文責 三枝


 Home
Home