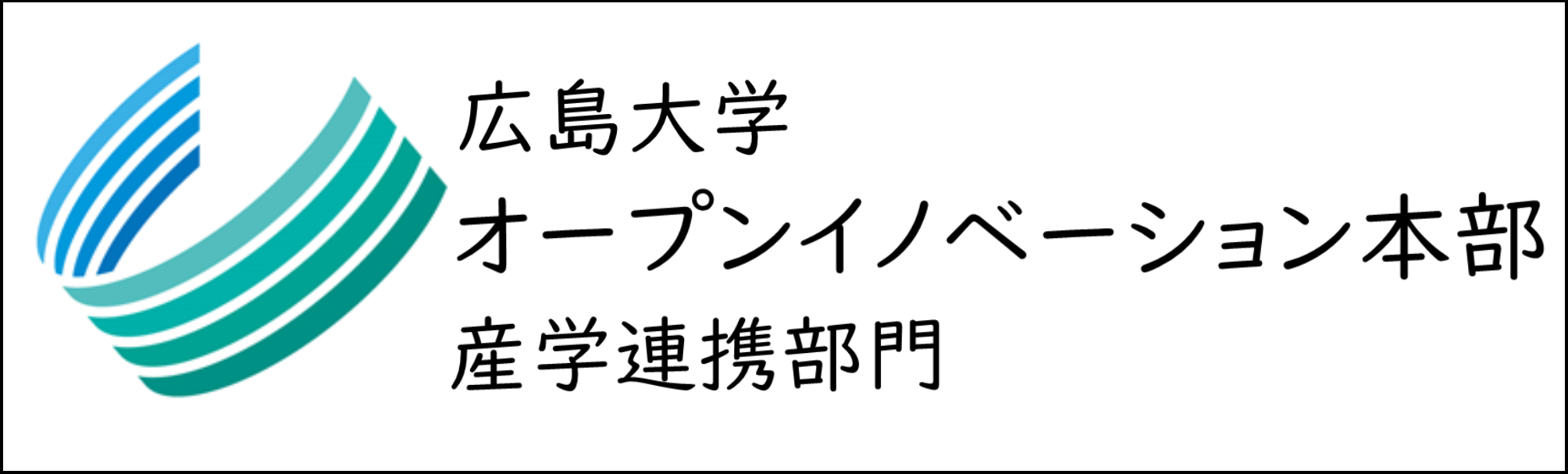『産学連携学会 第8回函館大会』が開催されます
産学連携に関する諸課題について、産学官の学識経験者や実務家が広く交流し、相互に啓発し合う場として、第8回年次大会が開催されます。 広島大学からは5件の発表を行います。
【開催日時】 平成22年6月24日(木)~6月25日(金)
【会場】 ロジワールホテル函館
【広島大学発表】
●清水谷 卓(産学・地域連携センター 産学連携フェロー) 『廃棄物処理分野における北西イングランドの研究機関との国際産学連携ネットワーク』 広島大学は平成20年度に文部科学省「産学官連携戦略展開事業(戦略展開プログラム)-国際的産学官連携の推進-」の採択(中四国地域で唯一)されたことにより、本格的な国際産学連携活動の組織作りが開始された。この事業において内部的な国際産学連携の体制づくり(案件が浮上してから契約締結までの過程)が必須事項である一方、その前段階である国際産学連携の案件を見つけて来る機能の充実化も重要事項である。題目の活動は、後者に着目したものであり、その目的を、①本学における自立的な国際産学官連携(安定的な外部資金獲得)の仕組みづくりに寄与すること、及び、②地域の特性を踏まえた大学の取り組みの独自性が示された成功事例を作ること、と位置付けた。本活動が発展途上であるため、本研究発表の内容は現時点までの活動状況の評価に留めることとする。
●クスタース ハロルド(産学・地域連携センター 産学官連携コーディネーター) 『広島大学のタイ国における産学連携活動』 本発表では、広島大学の国際的な産学連携の組織を取り上げながら、タイにおける活動、タイで使用している戦略をイメージ化したモデル及び今までの具体的な実例を取り上げながら説明する。
●森下 浩明(産学・地域連携センター 産学官連携コーディネーター) 『地域金融機関との人材交流による産学連携推進』 広島大学の産学連携活動の課題の一つに、「中小企業との共同研究が少ない」ことが挙げられる。この理由としては、①地域の中小企業は大学に対して敷居の高さを感じるため、技術的な課題があっても大学へ相談をしづらい、②大学側は地域におけるネットワークの不足から地域へ十分なアプローチが出来ない、ということが考えられる。この課題を解決すべく、取引先に中小企業が多い広島銀行と広島大学は包括協定に基づいた人材交流による産学金連携推進に取り組んでいる。このたび広島銀行から広島大学へ出向し活動する機会を得たので、金融機関が産学連携に取り組むメリットを再度確認しつつ、我々のこれまでの取り組みの経緯・成果事例・今後の課題について報告する。
●鈴藤 正史(産学・地域連携センター NEDOフェロー) 『尾道産ハッサクを丸ごと使った商品の開発』 広島大学と県内の食品企業が共同研究の成果を元に尾道産ハッサクを使った新しい商品を開発した。この過程で広島大学が共同研究の他に様々なサポートを行った。例えばコーディネータが中心となり、広島県産の地域ブランド商品として企画、販売の促進を行った。また、一部の商品では企業側からの要望で文系教員が関与して商品デザインをプロデュースした。これらの広島大学が共同研究とは別に行った連携の仕組みと活動について紹介する。
●小山 知秀(三次市役所 地域振興部企画調整課) 『広島大学と三次市との地域連携活動』地方自治体と大学との包括協定を活かした地域の中小企業と大学との連携支援について,事例をもとに考察する。2007年10月に三次市と広島大学が包括協定を締結し,2009年度にこの協定に基づいて,三次市職員が広島大学に出向した。この職員がコーディネーターとなり,三次市内にある中小企業と広島大学研究者との共同研究・開発をいかに支援したかについて報告する。
【お問合わせ先】 広島大学 産学・地域連携センター 国際・産学連携部門
TEL:082-421-3631 FAX:082-421-3639 E-MAIL:techrd@hiroshima-u.ac.jp (@は半角で入力して下さい)


 Home
Home