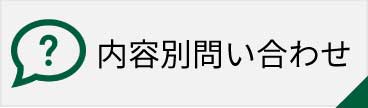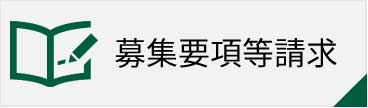初等教育学プログラム
初等教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実施します。
1年次には,教養教育科目や外国語科目や平和科目を履修し,専門教育の基盤づくりを行うとともに,平和を希求する人間を育てる教育界に貢献するための広い視野と能力を培います。また,専門基礎科目である「算数」,「教職入門」,「小学校教育実習入門」等を履修し,初等教育教員に関する基礎的な知識・技能を修得します。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修して,専門教育の基盤づくりを行うと共に,「初等国語」,「初等理科教育法」,「教育の思想と原理」,「教育と社会・制度」等を履修することで,初等教育教員に関する基礎的な知識を広く修得するとともに分野間の理解を深めます。
3年次には,「教育方法・技術論及び情報活用教育論」や各教科の指導法等の専門科目を主として履修し,専門的・実践的な知識・技能を修得します。また,「教育実習指導A」,「小学校教育実習Ⅰ」では,小学校で実習を行い,教職全般に関する実践的知識・態度・技能,及び自ら思考・判断・表現する能力を高めます。
4年次においては,3年次までの授業科目の履修を踏まえた「教職実践演習」を行うことで,初等教育教員としての資質や課題を確認し,必要に応じて補充・深化します。また,「卒業研究」では,本プログラムを通して修得した専門的な知識・技能・能力を活用して独自のテーマに主体的・協働的に取り組むことで,自らの問題を発見して解決する力を培います。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
特別支援教育学プログラム
特別支援教育学プログラムでは,(1)教養教育,(2)専門基礎科目,(3)専門科目,(4)卒業研究の履修を通して,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践します。
(1) 教養教育では,「教養ゼミ」などの大学教育基礎科目,外国語科目や情報・データサイエンス科目などの共通科目等を履修し,現代の社会や教育の要請に応える総合的な資質と能力を養います。
(2) 専門基礎科目では,「教職入門」「教職実践演習」「児童・青年期発達論」「初等国語科指導法」等,教員を目指すために必要となる学校制度や児童等の心理・発達の理解及び小学校の教科指導に関する基礎的知識・理解を深め,実践的能力・技能を身に付けます。
(3) 専門科目では,次のような教育課程を編成します。
1) 1年次には,「特別支援教育総論」をはじめ各障害種の心理学及び基礎論に関する科目を履修し,特別支援教育に関する専門性を高め,特別支援学校で活躍する教員を目指すために必要となる基礎的知識・理解力を身に付けます。
2) 2年次には,3つの専修【第一専修(視覚障害教育),第二専修(聴覚障害教育),第三専修(知的障害・肢体不自由・病弱教育)】に分かれ,各障害種の指導法に関する科目を中心に履修し実践的能力・技能を高めますが,同時に,「LD等教育総論」等の取得免許領域に関連した教育的課題に対応した授業科目も履修することで,専門的・総合的な知識・理解力や方法論,視座を修得します。
3) 3・4年次には,所属専修の障害種の指導法に関する科目及び「重複障害教育総論」「特別支援教育支援技術総論」などの関連した授業科目を継続的に履修するとともに,「特別支援学校教育実習」(3年次)や「特別支援学級教育演習」(4年次)の履修を通じて,障害のある児童等の指導にあたるための実践的能力・技能を高めます。
4) 教育職員免許法に定められている科目に加え,「視覚管理」「聴覚障害乳幼児指導法」「知的障害職業教育実践演習」「学びのユニバーサルデザイン入門」等の「発展科目」を履修することで,専門領域の学びをさらに深めます。
(4) 卒業研究では,(1)~(3)の授業科目の履修を踏まえ,3年次から4年次にかけて行う特別支援教育に関する研究を通して,研究計画の立案や文献検索,研究内容の発表などといった知的能力・技能を身に付けます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
理科教育学プログラム
理科教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践します。
1年次には,教養教育科目や外国語科目を履修し,専門教育の基盤づくりを行うとともに,平和を希求し国際化社会に貢献するための広い視野と能力を培います。また,専門基礎科目である「自然システムの理解(物理,化学,生物,地学)」や専門科目である「各分野リテラシーⅠ」を履修し,理科の教育内容に関する基本的な知識を修得し,理解を深めます。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修して,専門教育の基盤づくりを行うとともに,「自然システム(理科)教育法Ⅰ・Ⅱ」や「自然システム理解実験(物理・化学・生物・地学)」などの専門基礎科目を履修することで,科学教育に関する基礎的な知識を広く修得するとともに分野間の理解を深めます。さらに,専門科目として「理科カリキュラム論」,「理科授業プランニング論」,「各分野リテラシーⅡ」,「教材内容論I(物理,化学,生物,地学)」などを中心に学習を進め専門性を深めます。
3年次には,科学教育を体系的に学ぶために,各自の興味関心に応じて6つの研究領域 (科学教育学,科学教育方法学,物理学,化学,生物学,地学)の一つを選択します。その研究領域に関連した授業科目を重点的に選択履修し,専門的な知識を修得します。また,「自然システム教育研究法」では,中等理科教育に関連した研究の手法を修得し,研究力を高めます。
4年次においては,指導教員のもとで卒業研究を行います。卒業研究では,本プログラムを通して修得した専門的な知識,技能,能力を活用して独自のテーマに取り組むことで,自ら問題を発見して解決する力を培います。
本プログラムには選択科目として,「教職専門科目」,「教育実習」があり,教職専門科目では,中・高等学校の理科教員免許を取得するために必要な知識と技能を修得します。また,教育実習では,附属学校において理科に関する授業実践を行い,教材研究・授業実践能力を高めるとともに,生徒との関わり方や授業の進め方について実践的に学び,理科教員となるための資質を高めます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
数学教育学プログラム
数学教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実施します。
1年次には,教養教育科目や外国語科目を履修し,将来の数学教育研究を行っていくための幅広い学識と素養を身につけます。また,「微分積分学Ⅰ,Ⅱ」,「線形代数学Ⅰ,Ⅱ」を履修し,現代の数学に関する基礎的な知識を修得します。さらに,専門基礎科目として「数学教育方法論」を履修します。これらは専門教育への導入であるとともに,プログラム全体の基礎力を形成します。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修して,専門教育の基盤づくりを継続するとともに,「数学教育学概論Ⅰ」,「代数学概論Ⅰ」,「幾何学概論Ⅰ」,「解析学概論Ⅰ」,「数理統計学概論」等を履修し,数学教育の原理と方法に関する基礎的・基本的な知識・技能,ならびに教材分析及び開発を行うために必要な,教科内容に関する広い知識・技能と高い数学的な能力を獲得します。これらは,プログラムを支える骨格部分となります。
3年次には,「数学教育カリキュラム論」等を履修し,数学教育の原理と方法に関する知識・技能を深めます。また,「代数学研究法Ⅰ」,「幾何学研究法Ⅰ,Ⅱ」,「解析学研究法Ⅰ,Ⅱ」等の専門科目を主として履修し,これまでに獲得してきた能力を土台として,教科内容に関するより深い知識・技能を獲得し,実践的な能力と態度を形成します。
4年次においては,卒業研究を中心に履修し,本プログラムを通して修得した専門的な知識・技能・能力を活用して独自のテーマに取り組むことで,自ら問題を発見して解決する力を培います。また,あわせて専門科目も履修することによって,数学教育の理論的・実践的研究を行うための知識・技能を深めます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
技術情報教育学プログラム
技術情報教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針をもとに体系的に教育課程を編成し,実践します。
1年次には,大学教育の基礎となる一般的な知識・技能も含めた教養を広く培います。また,一部専門基礎科目も履修することで,技術・情報教育と情報内容学の基礎的内容を学習します。
2年次には,技術教育(教育学・内容学),情報教育(教育学・内容学)の基礎となる専門基礎科目,ならびにこれに続く専門科目を履修します。ここでは,各分野の「概論」等を学習することで,技術や情報,関連する教科の知識・技能を育成します。
3年次には,2年次までに学習した内容をさらに発展させる専門科目を履修します。ここでは,各分野の「演習」,「実習」等を学習することで,技術や情報に関する製作・制作活動の実践力と態度,関連する教科の実践的な知識・技能を育成します。
4年次には,卒業研究(卒業論文)を主体としながら,発展的・応用的専門科目を学習します。ここでは,技術や情報,関連する教科の問題をグローバルな視点から発見・具体化し,製作,制作,調査,実験等により問題解決を図る総合的な能力と創造的な態度を養います。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
社会認識教育学プログラム
社会認識教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践します。
学位の取得には,本プログラムで開講される授業科目を選択履修することによって修得する128単位を条件としています。その内訳は,教養教育科目32単位,専門基礎科目16単位,専門科目40単位,専門選択科目と自由選択科目32単位,卒業研究8単位です。
1年次から,専門基礎科目と専門科目に関する授業科目がはじまります。教養教育は専門教育の基盤づくりを担い,人文・社会科学に関する基本的な知識・理解を得るとともに,外国語能力が向上することになります。
専門教育科目のうち社会系に関連する科目は,社会科教育,地理教育,歴史教育,公民教育等を取扱う「社会認識教育学」科目と,地理認識内容学,歴史認識内容学,市民性内容学,社会科学認識内容学からなる「社会認識内容学」科目のほか,選択科目で構成されています。
各科目領域は,基礎入門から理論研究,実習演習へと配しており,各領域を順次履修することで,各知識・理解,能力・技能の水準を徐々に上げ,中等社会系教員として必要な諸能力を無理なく修得できるように構造化されています。
各年次の履修基準は,1年次では教養教育科目の14単位以上,2年次では教養教育科目累計28単位以上,専門科目累計28単位以上,3年次では専門科目累計56単位以上を各々修得していることです。
卒業論文は,本プログラムがめざす中等社会系教員養成の最終到達点です。手順としては,3年次に開催されるゼミ分け説明会に参加した上で,指定された期日までに卒業論文指導教員の希望調書を提出します。3年次第3・4ターム以降,論文執筆に必要な内容を含む授業科目のほか,主要な研究領域の授業科目を重点的に選択履修します。4年次第1・2タームには,各領域の卒業研究演習で適切な指導を受け,第3・4タームには本格的に卒業論文の作成・執筆に入ります。4年次1月末に卒業論文を提出し,2月にプログラムの教員及び学生・大学院生に向けて発表する卒業論文発表会に臨みます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
国語文化教育学プログラム
国語文化教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践します。
教養教育における幅広い教養とコミュニケーション能力,情報活用能力を身につけるための授業科目の基盤の上に,専門教育科目の教育課程を次の履修科目群のもとに編成しています。
1)専門基礎科目 2)専門科目(発展科目I) 3)専門科目(発展科目II)
4)専門選択科目・自由選択科目 5)卒業研究科目
これらの科目群は,次のように本プログラムの目的・目標と対応し,段階的に履修することで,身につけるべき知識・理解,分析・総合力,探究力を修得できます。
(1) ことばとその文化の教育に関する知識・理解
専門基礎科目の「国語文化基礎ゼミI」,「同II」と,発展科目Iの国語文化内容系科目(国語学・国文学・漢文学・書写書道の諸分野)及び国語文化実践系科目(国語科教育学の諸分野)を履修し,ことばとその文化の教育に関する基礎的知識を身につけるとともに,それらを相互に関連したものとして理解する。
(2) ことばとその文化の教育に関する分析力・総合力
発展科目II(国語文化内容系科目及び国語文化実践系科目)と,専門選択科目のうち教職関係科目(「教職入門」,「教育の思想と原理」他)を履修し,ことばとその文化の教育に関するより専門的な知識と,分析的に思考し総合的に判断する力を身につける。
(3) ことばとその文化の教育に関する反省的実践力
専門選択科目のうち教育実践系科目(「中・高等学校教育実習入門」「同観察」「教育実習指導B」「中・高等学校教育実習I」「同II」「教職実践演習」)を履修して,ことばとその文化の教育に関する反省的実践力を身につける。
(4) ことばとその文化及び教育に関する探究力・創造力
卒業研究科目(国語文化研究法+卒業論文ゼミ+卒業論文)を履修し,ことばとその文化の教育に関する探究力と創造力を身につける。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
英語文化教育学プログラム
英語文化教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実施します。
1年次には,教養教育科目や外国語科目を履修し,専門教育の基盤づくりを行うとともに,21世紀にふさわしい学校教育の創造や生涯学習社会の構築に貢献するためのグローバルな視野と能力を培います。また,専門基礎科目である「英語コミュニケーション演習Ⅰ・Ⅱ」,「英語文学概説」を履修し,英語に関する基礎的な知識を修得します。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修して,専門教育の基盤づくりを行うとともに,「英語学概説Ⅰ」,「英語教育学概論Ⅰ・Ⅱ」の専門基礎科目や「英語教材構成論」等の専門科目を履修することで,英語及び英語教育に関する基礎的な知識を広く修得するとともに分野間の理解を深めます。
3年次には,「英語学概説Ⅱ」,「コミュニカティブライティングⅠ・Ⅱ」の専門基礎科目や,カリキュラム,評価,異文化理解に関する専門科目を主として履修し,専門的な知識を修得します。さらに,「英語教育研究法」や「英語教育研究Ⅰ」を履修し,英語教育研究に関する基礎的な知識を修得します。また,「中・高等学校教育実習Ⅰ」又は,4年次の「中・高等学校教育実習Ⅱ」では,英語科教員としての基礎的な教育実践力を身につけます。
4年次には,「英語教育研究Ⅱ」を履修し,英語教育研究に関する知識をさらに深めます。卒業研究(卒業論文)では,本プログラムを通して修得した専門的な知識,技能,能力を活用して独自のテーマに取り組み,自ら問題を発見して解決する力を身につけます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
日本語・日本文化教育学プログラム
日本語・日本文化教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実施します。
1年次には,教養教育科目や外国語科目を履修し,専門教育の基盤づくりを行うとともに国際社会に貢献するための広い視野と能力を培います。また,専門基礎科目である「日本語教育学基礎論」や「日本語教育課程論」等を履修し,日本語教育に関する基礎的な知識を修得します。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修して専門教育の基盤づくりを行うとともに,「異文化接触と文化学習」,「社会言語学」,「第二言語習得と指導」,「年少者日本語教育」,「言語教育と社会」等の専門基礎科目を履修します。
3年次には,「文化社会学演習」,「言語人類学演習」,「日本語教育評価法演習」等の専門科目を主として履修し,専門的な知識と研究の方法論を修得します。また,国内(「日本語教育実習研究」)や海外(「日本語教育海外実習研究A」)の日本語教育機関において実習を行うことで教育実践力と省察力を高めます。
4年次においては,卒業論文で,本プログラムを通して修得した専門的な知識,技能,能力を活用して独自のテーマに取り組むことで,自ら問題を発見して解決する力を培います。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
多文化・グローバル教育学プログラム
多文化・グローバル教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもと に教育課程を編成し,実施します。
1年次には,教養教育科目や外国語科目を履修し,専門教育の基盤づくりを行うとともにグローバル社会に貢献 するための広い視野と能力を培います。また,専門基礎科目である Education in Multicultural Society , Introduction to Peace Education Theory,Introduction to International Educational Development 等を履修し,多文化教育・平和教育・国際開発教育に関する基礎的な知識を修得します。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修して専門教育の基盤づくりを行うとともに,Designing Curriculum for Diverse Children , Curriculum Development of Peace Education , International Educational Development and Global Partnership 等の専門基礎科目を履修し,多文化教育・平和教育・国際開発教育に関する基礎的な知識を深めます。
3年次には,Critical Peace Pedagogies, International Educational Development Project Planning and Assessment 等を履修し,専門的な知識を修得します。また,観察実習科目として Exploratory Teaching Practicum, Observation of Peace Education, Observation of International Education Development を履修することにより教育分野において多文化共生・平和構築・国際協力を実践するための能力を高めます。
4年次には,卒業論文で,本プログラムを通して修得した専門的な知識,技能,能力を活用して独自のテーマに 取り組むことで,自ら問題を発見して解決する力を培います。
上記のように編成した教育課程では,多文化共生教育,平和教育,国際開発教育を体系的に学び,講義,演習, 実習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,課題探究型の授業,オンライン等も活用した教育,学習を実践します。国際バカロレア認定校,インターナショナルスクール,国際協力機関などでの観察実習やインターンシップも多数設定し,海外留学も強く推奨します。専門科目の中核は英語で行われるため,教養教育科目も工夫をすれば,英語のみで卒業ができ,英語を用いた実践力が向上します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と,本プログラムで設定する到達目標 への到達度の2つで評価します。
健康スポーツ教育学プログラム
健康スポーツ教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実施します。
1・2年次では,教養教育科目とともに「陸上競技」,「体つくり運動・器械運動」,「ダンス」,「水泳」,「武道A(柔道)」,「球技A(バレーボール)」,「球技B(サッカー・ソフトボール)」,「球技C(バスケットボール)」,「球技D(テニス)」,「野外活動演習」などの各種スポーツ科目に関する指導内容について十分な知識や技能を獲得します。並行して,学問を体系的に学ぶための「健康・スポーツ総論」を履修します。これらを総合的に学ぶことで,学校体育,社会体育などの各種の運動指導場面を考慮した実践的指導力と生涯スポーツへの素養を育みます。
3年次以降は,「スポーツ生理学」,「スポーツ医学」,「スポーツ経営学」,「スポーツ心理学」,「コーチング論」などを学びます。各授業科目で理論的に学んだ内容をもとに,「保健体育科教育方法・評価論」や各実技科目における「指導演習」でカリキュラム作成,教材開発,指導案作成などの実際的な課題遂行と実践的能力を育みます。
4年次では,プログラム全体を通しての能力開発を行います。特定の専門領域・専門科目に集約し,卒業論文としてまとめることを目指します。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
家政教育学プログラム
家政教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践します。
本プログラムは,教養教育のほかに,専門基礎科目と専門科目から成り,卒業研究を履修することによって到達目標が達成されます。
1年次には,専門教育を受ける準備段階として教養教育科目の履修が中心となります。家政教育を学ぶために必要な科学的な視点と教養及び総合的資質・能力を身につけます。また,専門教育の基礎段階として,一部の専門基礎科目を学びます。
2年次には,その他の専門基礎科目と各分野の専門科目において家政の課題を理解し,多様な視点でとらえることができる能力と家政教育に関わる基本的な能力を身につけます。
3年次には,専門教育の発展段階として専門科目を中心に履修します。2年次の学修を発展させ,自立した生活者として家庭生活及び人間生活環境の創造に関わる教育実践力を身につけます。また,それまでの学修に基づいて,各自関心のある研究テーマに即して卒業研究をスタートさせます。
4年次には,卒業研究の遂行と完成により科学的な思考力を培うとともに,学校教育並びに生涯教育において人間生活教育の理論と実践を融合してグローバルな視点で社会に貢献できる能力を身につけます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
音楽教育学プログラム
音楽教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を学生に実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践します。
1年次には,専門基礎科目である「ソルフェージュ」,「声楽基礎研究」,「鍵盤楽器基礎研究」,「作曲基礎研究」等を履修し,音楽に関する基礎的な知識と技能を修得します。併せて,教養教育科目や外国語科目を履修し,音楽分野に偏らないグローバルな視野と能力を育成するとともに,社会と平和に貢献するための自覚を促します。また,「中・高等学校教育実習入門」を履修し,教育実習に対する基本的な心構えを学びます。
2年次には,専門基礎科目及び教養教育科目を引き続き履修し,視野を広げる他,「教職入門」,「教育の思想と原理」,「教育と社会・制度」等の教育職員免許状取得に係る授業,及び「音楽科教育方法論1」,「作曲」,「声楽」,「ピアノ」,「管弦打楽器」等の専門科目を履修し,教育と音楽について理論と実技の両面から専門的に学びます。また,教育実習の現場を視察する「中・高等学校教育実習観察」を履修し,音楽科授業を様々な視点から分析する能力を養います。
3年次には,教職必修科目及び「日本音楽演習」等の専門科目を引き続き履修する他,各附属学校における「教育実習指導B」及び「中・高等学校教育実習Ⅰ」を履修し,教育現場での実践力を培います。また「コンサート・マネージメント」を履修し,実際に定期演奏会の企画・運営を行うことにより,協働して問題を発見し解決する能力を高めます。
4年次には,本プログラムで修得した専門的な知識・技能・能力を活用し,独自のテーマに基づいた「卒業論文」にまとめます。また,引き続き専門科目を履修することにより,器楽・声楽・作曲・音楽教育学に関するより高度で専門的な研究を継続することができます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
美術教育学プログラム
美術教育学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実施します。
1年次には,教養教育科目や外国語科目を履修し,専門教育の基盤づくりを行うとともに社会及び美術教育に貢献するための広い視野と能力を培います。また,専門教育の基礎段階として,美術教育,絵画,彫刻,デザイン, 美術理論・美術史における専門基礎科目および一部の専門科目を履修し,美術教育に関する基礎的知識,技能を修得します。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修して,専門教育の基盤づくりを行うとともに,専門基礎科目および専門科目を履修することで,美術教育を学習していく上で必要な概括的かつ基礎的知識と技能を獲得し,領域間の理解を深めます。2年次までに,1年次の専門基礎科目に加え,工芸を含むすべての専門領域において基礎的内容を一通り学びます。
3年次には,専門科目を主として履修し,発達過程に即した美術教育を実践するための必要な専門的知識を修得します。また,卒業研究領域を決定し,それぞれ関心のあるテーマに即してより専門性の高い内容を学び,卒業研究のための基礎的な能力を高めます。
4年次には,美術教育に関する発展的内容を学んで学習を深めます。また,卒業研究では,論文作成・作品制作を行います。そこでは,本プログラムを通して修得した専門的な知識,技能,能力を活用して独自のテーマに取り組むことで,自ら問題を発見して解決する力を培います。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
教育学プログラム
教育学プログラムでは,学生が教育に関するさまざまな理論や思想,事象,課題について,哲学的・歴史的・社会学的・国際比較的視野に立って学習し研究するとともに,教育方法・技術や教育課程,学校経営,教育行財政,社会教育・生涯学習,幼児教育,高等教育をめぐる具体的問題群についての理論的・実践的検討を行いうるように構成されています。本プログラムでは到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実施します。
1年次には,教養教育科目を履修し,専門教育の基盤づくりを行います。また,「教育哲学」から「高等教育概論」まで11領域にわたって開設された専門基礎科目を履修し,教育関連諸科学の基礎的知識を修得します。
2年次には,教養教育科目や専門基礎科目を引き続き履修するとともに,教育哲学から幼児教育学まで10領域にわたって開設された領域基礎演習を履修することで,教育に関する資料・情報・データの収集力と具体的な教育課題に対する分析力・判断力,外国語運用能力や調査・研究の基礎となる教育学の研究手法を修得します。2年次までに履修した領域基礎演習や「教育学総合演習A」をもとに,学生は自分の研究関心に即して特定領域を選択し,3年次以降に備えます。
3年次には,領域基礎演習や研究法に関する専門科目を引き続き履修します。それとともに,学生は特定領域の研究室に所属します。自分の選択した領域の課題演習を履修することで,指導教員による少人数・個別指導を受けながら卒業論文のテーマを設定し,「教育学総合演習B」で卒業論文の構想発表を行います。
4年次には,自分の選択した領域の課題研究を履修し,卒業論文作成に取り組みます。卒業論文では,教育の専門家に求められる研究開発能力・政策立案能力や,生涯にわたって自らの能力・学識を開発しつづけるための自己学習力を培います。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。
心理学プログラム
心理学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,人間の心の仕組みや働きを理解し,心の測定法やデータの収集・分析などの方法を修得し,それらを実践し新たな知の探求ができるための基礎を育成します。また,実社会において生じる心や行動の問題の解決のための基礎となる知識や技能を育成します。そのために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践します。
心理学プログラムの教育課程は,(公益社団法人)日本心理学会が認定する「認定心理士」の申請に必要な科目,並びに公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号)において大学における公認心理師となるために必要な科目として示された科目を充たすものです。
1年次には,「心理学概論A・B」,「大学教育入門」及び英語などの教養教育科目を履修して専門教育の基礎づくりを行うとともに,「心理学基礎実習」を履修し,心理学の研究を体験し,心の測定法やデータの収集・分析などの基礎的な方法を身につけます。
2年次には,教養教育科目を引き続き履修するとともに,「知覚・認知心理学」,「学習・言語心理学」,「社会・集団・家族心理学」,「教育・学校心理学」,「発達心理学」,「臨床心理学概論」などの心理学各領域の概論を履修し,心の仕組みや働きを理解するための標準的な知識を身につけます。また,「心理学研究法」,「心理学統計法I・II」,「心理社会調査法」などの研究法科目を履修し,人間の心について理解するための方法・技能を身につけます。
3年次には,心理学の各領域の特論として,「神経・生理心理学」,「対人心理学」,「教育相談」,「児童・青年期発達論」,「乳幼児心理学」,「障害者・障害児心理学」などを履修し,心の仕組みや働きを理解するための発展的・応用的な知識を身につけます。
3-4年次には,学士課程のまとめとして,実際に心理学が使われている複数の職場を見学する「心理実習I・II」や,研究を遂行する能力・技能を身につけるために「心理学実験」,「課題研究I・II」を履修し,現代社会における人間の心や行動に関する問題解決への意欲や態度を形成します。
また,2-3年次にかけて,心理学の実践・応用領域や関連領域の科目として,「心理学的支援法」,「健康・医療心理学」,「福祉心理学」,「司法・犯罪心理学」,「精神疾患とその治療」,「関係行政論」などの科目を履修し,実社会において生じる心や行動の問題の解決に寄与するための知識・技能を身につけます。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践します。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,本教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価します。


 Home
Home