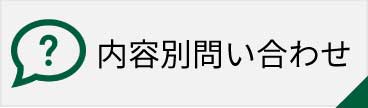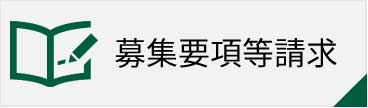医学プログラム
1) 医師としての豊かな人間性を涵養し,また,専門職職業人(プロフェッショナル)として人々の健康を守る使命感・責任感を陶冶するため,6年間を一体とする計画的な専門職養成教育を行う。また,入学後早期から実際の医療現場に接する実習を行うことで,医師の仕事と他の医療職の業務を理解し,医師となるべき心構えと医師のあるべき態度を自ら考え自覚することを促す。
2) 将来,どの専門分野に進もうと,その土台となる幅広い知識と技能を身につけるため,統合的な講義体系を組み,専門分野の概念にとらわれない教育を行う。また,医学教育モデル・コア・カリキュラムに準拠する教育計画のもと,基本的な知識や技能を遺漏なく体系的に修得させる。
3) 臨床実習には見学型および診療参加型実習を採用し,医療現場で医師としての業務を体験することで知識・技能・態度を実践的に学ぶ。これらを統合して診療にあたる能力を身につけることで,卒業後の臨床研修に連続して移行できる診療能力を確立させる。
4) PBL(Problem-based learning)テュートリアルやTBL(Team-based learning)などのグループワーク教育により,学生自身が何をどれだけ学ぶかを考えながら学習を進められるような主体的な学習姿勢を養う。また自ら問題点をみつけそれを解決する姿勢と能力の確立も目指す。このため,知識伝達型講義は全授業時間の半分程度とし,残りは演習や小グループによるディスカッションとする。これらを通して,生涯にわたって自らの努力で向上し続ける意欲と学習の習慣を修得する。
5) 低学年のうちからグループ学習を積極的に取り入れることで,協働することの重要さを学び,チームの一員として責任をもってチームに貢献する姿勢の確立を図る。また,信頼関係に根ざした良好な人間関係を構築するためのコミュニケーション能力を修得するため,診療参加型実習によって患者との良好な人間関係を築く技術を修得させる。
6) 疾病の予防や健康に関する問題を社会の中で捉え,保健制度や医療経済についても十分な知識を持たせるため,演習や実習を通じて保健医療制度における医師の役割や責務への理解を促す。また,地域医療実習によって地域社会における医師の果たす役割を理解させ,すべての学生が県内各地域の医療機関で実習することで医療と地域住民の生活との関係を理解し,地域の抱える保健・医療上の問題を認識させる。
7) 科学的な思考と方法論を十分身につけるため,臨床診療を行うための知識や診療技術の教授と並行して,医学研究にも参画させる。これにより,医学研究の意義と重要性を理解し,自らも医学の発展に寄与しようとする気概と研究心を養う。
8) 入学時に全学生にTOEIC(R)IPテスト を受験させ,個々の英語力を評価し,外国語教育研究センターの教員による英語の集中講義を取り入れ,臨床で役立つ実践的な英語力を養い,英語による高いレベルのコミュニケーション能力を修得させる。また,医学研究実習では,海外の研究施設で研究を行うことも選択させ,研究活動を行いながら国際交流能力の向上を図る機会を設ける。
9) 社会人としての幅広い教養を備え,また,医学的問題を幅広い視野からとらえる能力を併せ持つため,広い視点での教養教育を行う。また,化学,物理学など,高校で学ばない科目があることで専門教育に支障をきたさないよう,高校での未修得科目に対する補充教育も行う。さらに広島という独自な地域性を考慮しつつ,グローバルな視野で常に平和を希求する人材を養成するための教養教育も行う。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践する。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,各教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価する。
看護学プログラム
本プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を学生に実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践する。
第1ステップ:1年次で,「豊かな人間性と幅広い教養,専門科目を支える教養教育科目」「人間の心身の機能に関する専門基礎科目」「看護実践の基礎となる専門科目」を履修し,複眼的な視野で広範な教養を育むとともに,健康と看護について深く探求するための基礎的知識を習得する。
第2ステップ:2年次に,「疾病の予防,発症,治癒に関する専門基礎および専門科目」「健康と環境に関する専門科目」「看護基礎技術に関する専門科目」「ヘルスケアシステムに関する専門科目」の科目群を中心に学習を進め,看護学に関する専門知識や人々との援助的関係を形成するために必要な能力を深める。また,妊産婦・新生児から高齢者,維持期からEnd-of-life期まで,健康課題を有しながら地域で療養・生活する人々を,看護職としてどのように支援するのかの視点を学ぶ。さらに,災害看護の基礎知識についても学ぶ。
第3ステップ:3年次第1・2タームに,「個人と家族,地域の健康問題と看護に関する専門科目」を履修し,看護実践者として科学的に判断し計画的に実施するための基礎的能力を育成する。
第4ステップ:3年次第3・4タームと4年次第1・2タームで,「看護実践上の判断能力を習得するための臨地実習」を履修し,看護実践者に必要な基礎的能力と,保健医療福祉組織の中で他職種と連携・協働し,看護職者としての役割を果たす実践基礎能力を育成する。また,4年次第3・4タームでは,「卒業研究」を通して,より包括的に看護学を考究し,問題の発見と解決に向けた探求の基本姿勢を育成する。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践する。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,各教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価する。
・国際的な視点をもって,ヘルスケアを発展させられる人材の育成
入学時に全学生にTOEIC(R)IPテストを受験させ,個々の英語力を評価する。外国人教員による英語の講義や世界各地での海外研修や国際交流活動を取り入れ,実践的な英語力と国際感覚,グローバルに物事を考えることのできる思考や態度を養う。
理学療法学プログラム
理学療法学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践する。
1)理学療法の基礎知識・技能の修得
早期より専門教育を取り入れ,理学療法学的発想をもとに問題の発見と解決に向けた探求心を育む。講義や演習,実習を通じて,理学療法を展開するために必要となる基礎知識と技能・態度の修得に努める。さらに,段階的に臨床実習を経験することで,理学療法の実践に適合した知識,技能,態度の統合を確立させ,保健・医療・福祉に関わる理学療法士としての資質と自覚を高める。
2)チーム医療を担う人間性の形成
教養教育科目を通して,基礎学力の向上と人間的価値観を深め,医療倫理についても学ぶ。また,学部・学科を超えて他職種との連携により医療・福祉を考える多職種間連携教育(IPE)では,チーム医療について学ぶ。これらの実践の場として,臨床実習において,安全性や生命倫理に対する判断力,医療チームの一員として協同する技能と態度を修得する。
3)科学的思考力の修得
卒業研究では,理学療法の課題やニーズを的確にとらえ,理学療法学の学問として意義と重要性について学ぶ。科学的思考力を持って能動的に課題と向き合い,調査や分析,実験などに基づき解決する技能,研究成果を論理的かつ明確に伝える技能や態度を修得する。
4)国際社会・地域社会をリードする人材の育成
国際社会・地域社会の様々な場面に広く視野を向け,新たな価値を創造でき,世界の理学療法をリードする人材の育成を目指す。海外の理学療法現場やスポーツ現場,介護予防現場等でのフィールドワークを通じて,様々な社会の課題やニーズを学び,それらの解決に向けて主体的に考える態度を修得する。
作業療法学プログラム
作業療法学プログラムでは,プログラムが掲げる到達目標を学生に実現させるために,次の方針のもとに教育課程を編成し,実践する。
・1年次には,教養教育科目を通して教養,基礎学力の醸成を行うと同時に,「解剖学」「生理学」「リハビリテーション科学入門」などの共通専門科目,「作業療法学概論」「基礎作業学」「リハビリテーション概論」などの専門基礎科目の一部を開講し,作業療法学的発想のもとで問題の発見と解決に向けた探求の基本姿勢を育む。 光り輝き入試総合型選抜制度(大学院進学型)で入学した学生は,1年次より「プロジェクト研究演習」を履修し,早期から大学教員が実践する研究を体験し,大学院で行う研究活動に必要な知識と技術を養う。
・2年次には,作業療法学の学問的背景や基礎となる授業を中心とし,主に「解剖学実習」「生理学実習」「基礎運動学」「リハビリテーション整形外科学」「リハビリテーション精神医学」「リハビリテーション神経内科学」など必修科目を開講し,これらの科目を通して専門分野の基礎知識と技能・態度を修得する。また,国際交流,科学探索,地域交流に関連した科目を選択可能とし,主体的に各領域に特化した基本的な知識や技術を学ぶ。
・3年次には,主に「身体障害作業療法学演習」「精神障害作業療法学演習」「発達障害作業療法学演習」「老年期障害作業療法学演習」「日常生活活動評価学演習」などの専門科目を開講し,作業療法を展開するために必要となる,情報の収集・評価・報告および根拠に基づいた治療に関する基礎知識と技能・態度を修得する。さらに,夏期の短期臨床実習を計画し,学問分野と実務との関連についての理解を深め,より具体的な課題への取り組み方について学ぶことができる。
・4年次には,長期臨床実習を計画している。3年次までの教育課程で学んだ知識,技能,態度と作業療法過程を,実習施設において指導者による指導を受けながら作業療法の実践を行い,実践に適合した知識,技能,態度の統合を目指す。同時に,実習を通して対象者や家族,他職種とのコミュニケーションの重要性についても認識を深める。こうした経験を重ねることで,保健・医療・福祉に関わる作業療法の専門職としての資質と自覚を高める。また,3年次から開始した卒業研究を完成することで,専門的な問題を理解・整理し,調査や分析,実験などに基づき解決するための能力を身につけ,作業療法学の学問として意義と重要性についても学ぶ。
上記のように編成した教育課程では,講義,実技,演習等の教育内容に応じて,アクティブラーニング,体験型学習,オンライン教育なども活用した教育,学習を実践する。
学修成果については,シラバスに成績評価基準を明示した厳格な成績評価と共に,各教育プログラムで設定する到達目標への到達度の2つで評価する。


 Home
Home