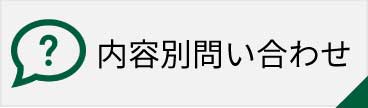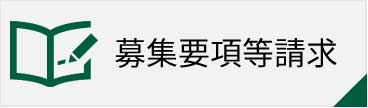広島大学は、2017年度から、教養教育の一環として、スポーツ、芸術、科学、ビジネスなど各界で活躍されているリーダーをお招きし、学部新入生を対象に講演を行っています。
本学では、大学で専門的な分野の学識を深めるのと同時に、幅広い教養、すなわちリベラル・アーツを生涯にわたって培っていくことが何より大切と考えています。
世界で活躍するリーダーたちが、どのような学生時代を過ごし、困難を乗り越えたのか。
大学での新しい一歩を踏み出す新入生に、間近で生きざまやスピリッツに触れてもらい、ワクワクする何かをつかんでもらうことを目的としています。
2025年度は、以下の方々に講義を行っていただきました。

学生時代、外務省での経験を踏まえ、これから社会に出て仕事をするうえで数学の知識や語学力、簿記など、幅広い知識を身に付けることが大切であることを学生たちに語られました。
被爆者との出会いをきっかけに、「なぜ、原爆が広島へ投下されなくてはならなかったのか」という思いを強く持ち、数々の取材を重ねながら執筆されたご自身の著書を紹介し、自身の足で取材を行うことへの熱意を語られました。

日本人の睡眠時間が短いこと、睡眠不足が免疫や脳のパフォーマンス低下を招くこと、睡眠時間と企業の経常利益との関連性など、睡眠に関する多様なテーマについて説明されました。
広島大学の歴史や特徴的な教育、世界に誇る研究拠点など世界トップクラスの大学を目指すための取り組みを紹介し、「広島大学を国際的な大学にしたい」と熱く語りました。

講演は、少子化や高齢化に関する人口問題、東広島市と他国との人口比較などについて選択式の問いを学生に示す、インタラクティブな形式で行われ、思い込みやステレオタイプに惑わされず、正確なデータや事実に基づき思考を巡らすことの大切さを説かれました。

学生からの質問に対し、メンタルの不調をどのように乗り越えたのか、コミュニケーションの方法や気を付けていたこと、ライバルを持つことで自分自身を高めたことなど、選手時代や監督時代のご経験をもとに丁寧に回答されました。

中学、高校、大学の間に日本とアメリカの両国を行き来して過ごした自身の学生時代の経験を振り返りながら、日本ではトレース型の学習が主流である一方、アメリカでは徹底的な調査とディベートを重視する教育が根付いていることや、異性や友人とのコミュニケーションのとり方の違いについて説明されました。
ご自身の幼少期から現在に至るまでの歩みを振り返り、多様なことに興味を持ち、ひたすら挑戦を続けてきた経験や、単身イタリアに渡り、世界最高峰のマリア・カラス国際声楽コンクールで優勝を成し遂げたことなど、世界で活躍されるまでの道のりを紹介されました。
意識と無意識をテーマに講演され、意識は単なる「飾り」にすぎず、私たちの行動は無意識の反射によるもので、行動の意味や理由付けは後から脳で作りだす「作話」であることを様々な実験や論文を示しながら説明されました。
ご自身の大学時代の経験、システムエンジニアとしてのキャリア、そして海外ビジネススクールでのMBA取得など、現在に至るまでの歩みを振り返りながら、株や投資が人生を豊かにし、日本をよりよく変えていくために欠かせないものであること、大学時代に資産運用について考え、学んでおくことの大切さを語られました。

講演は、AIアライメントをテーマに、「トロッコ問題」を例に挙げながら、自動運転における倫理的な選択などについて学生たちに問いかける、インタラクティブな形式で行われました。

これまでの取材を通じて出会った方々とのエピソードを振り返りながら、リーダーに必要な要素として「Passion(情熱)」「Mission(使命感)」「Action(行動力)」に加えて将来への「Vision(見通し)」を挙げられ、「リーダーには覚悟と度胸が必要」と語られました。


 Home
Home