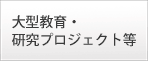記者会見の様子 |
 会見後取材の様子 |
広島大学大学院工学研究院の辻敏夫教授、大学院医歯薬保健学研究院の吉栖正生教授、東京大学大学院工学系研究科の金子成彦教授らを中心とする研究チームは、株式会社デルタツーリングとの共同研究により、健常者の循環器系の異変を早い段階で捉えるための、生体情報常時モニタリングシステムを開発し、東京オフィス(キャンパス・イノベーションセンター)で、記者説明会を開催した。
この研究成果は、平成26年11月以降、日本設計工学会の学会誌「設計工学」に掲載予定です。
【本システムのポイント】
1. 背部から心臓・血管系の音・振動情報(体表脈波(APW: Aortic Pulse Wave))をモニタリングできるセンシング技術および可聴化技術を開発
2. APW は、通常の生活をしながら非拘束の状態で計測可能なだけでなく、心電図から得られる心拍変動の時系列情報(RRI: R wave to R wave interval)と高い相関性を持つ
3. ベッドや椅子、自動車用シートへの設置を目指し、循環器系のモニタリングや日々の健康管理に応用
近年の交通事故のうち、運転中の「発作」や「急病」などが原因と思われる事故の中でも、心臓病と脳血管障害を原因とする事故件数は全体の半数を占めるといわれています。これらを防ぐためには、健常者自身が自らの健康状態を知り、特に異常が顕在化しにくい循環器系の異常を早い段階で捉え、医師に相談できるシステムを確立する必要性があります。
循環器系の異変を早い段階で捉えるためには、生体情報を常時モニタリングすることが有効ですが、これまでの常時モニタリングするため電力消費が少ない圧電センサは、外乱に対する脆弱性があるという問題点がありました。
そこで、ノイズや外乱の少ない音・振動情報を得るため、背中から捉えた場合、筋肉等により20Hz前後の音・振動情報に変換される心音に着目し、マイクロフォンセンサを用いた実験を行い、生体情報常時モニタリングシステムを開発しました。また、椅子等に内蔵し、捉えた心臓・血管系の音・振動情報を可聴化することにも成功しました。
本システムはベッドや椅子、自動車用シートへの内蔵を目指しています。循環器系の生体情報が常時、容易に入手できることにより、日々の健康管理ツールとしての活用に期待できます。
【お問い合わせ先】
広島大学大学院工学研究院
辻 敏夫 教授
TEL:082-424-7677
FAX:082-424-2387
E-Mail:tsuji*bsys.hiroshima-u.ac.jp(注:*は半角@に置き換えてください)

 Home
Home