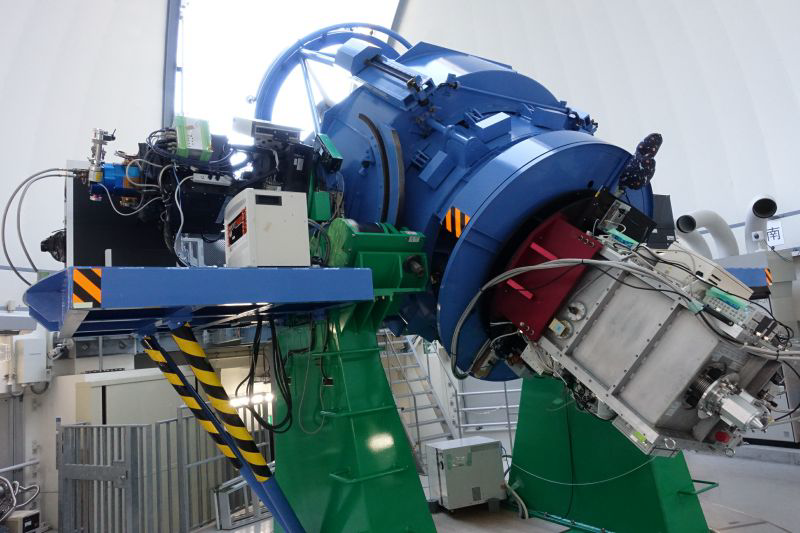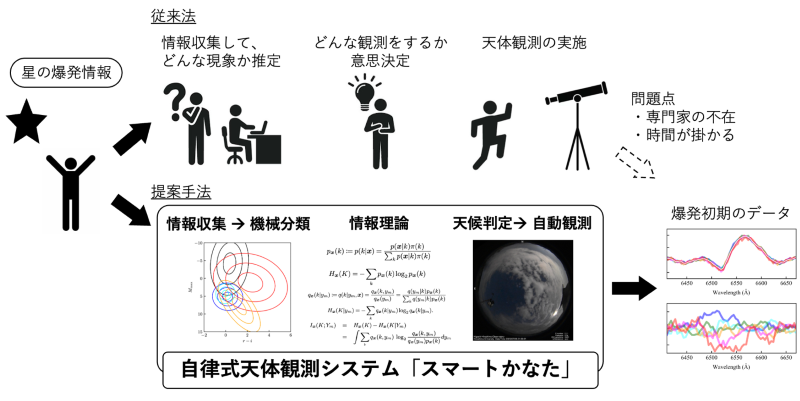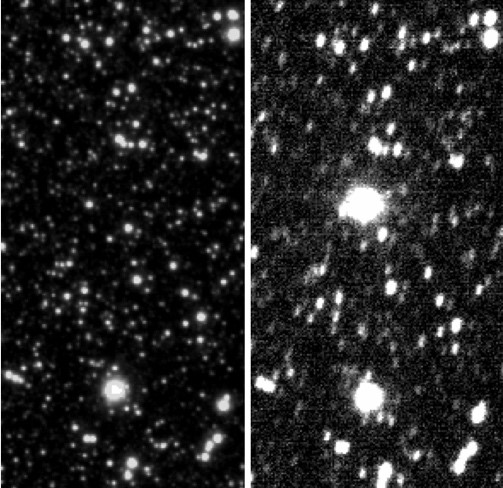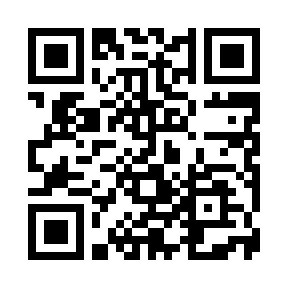<研究に関すること>
広島大学宇宙科学センター 准教授 植村誠
Tel:082-424-5765 FAX:082-424-5765
E-mail:uemuram*hiroshima-u.ac.jp
統計数理研究所 教授 池田思朗
E-mail : shiro*ism.ac.jp
<報道に関すること>
広島大学 広報室
E-mail : koho*office.hiroshima-u.ac.jp
統計数理研究所 広報室
E-mail : kouhousec*ism.ac.jp
(*は半角@に置き換えてください)

 Home
Home