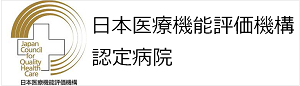広島市のA子さん(32)は2006年3月、妊娠7か月で受けた超音波検査で、おなかの赤ちゃんに重い病気が見つかった。
「ポッター症候群」。先天的に腎臓に問題があり、生まれたとしても長くは生きられない。「初めての赤ちゃんなのに、なぜ?」。毎日泣き続け、食事もとれず、家に引きこもった。
数日後、広島大病院の遺伝子診療部を、夫と両親と一緒に訪ねた。同部は「遺伝カウンセリング」を行う部門。様々な科の専門医や看護師らが、遺伝病や先天性の病気の情報を患者に提供し、チームで支える。「つらかったでしょう」。准教授で助産師の中込さと子さんは、背中をさすりながら話を聴いてくれた。「死ぬと分かっている子を産むのは怖い」「せめて痛くない出産はできないか」「次は元気な子を産めるのか」……。A子さんと家族の質問に医師が答えた後、中込さんからこう言われた。「今、考えないといけないのは、おなかの赤ちゃんのことですよ」1週間後にも同部を訪ねた。おなかの子は元気らしい。中込さんから尋ねられた。「赤ちゃんを、どんなふうに迎えたいですか?」このころから、A子さんの気持ちに変化が表れた。
そうか。見送るのではなく、迎えるんだ。私は、頑張って生きているこの子の母親。予定日までの2か月間、たっぷり愛情を注いで、笑顔で迎えなきゃ――。「病気や障害は深刻なことだけど、『いけないこと』と否定的に見ることではない」。中込さんの言葉がやっと理解でき、子へのいとおしさがこみ上げた。それからは、しっかりご飯を食べた。母と妹と3人で、赤ちゃんが寝るカゴや枕、布団、帽子を作った。名前は「陽来」と名付けた。日だまりのような温かさを与えてくれる、そんな意味を込めた。出産は5月、女の子だった。生後数時間の命かも、と言われていたハルちゃんは、予想以上に元気だった。多くの医師らと話し合いを重ねて決めた通り、痛みや苦しみを抑える最小限の治療を行いながら、家で一緒に生活できた。笑顔がすごくかわいかった。秋には家族で紅葉を見に出かけた。
そして翌07年1月。娘は、母親の腕の中で眠るように息を引き取った。7か月余りも頑張ってくれた。「ハルからは多くのことを教えられた。今は、娘を思い出すと温かい気持ちになる。遺伝カウンセリングのおかげです」。A子さんはその後、2人の子に恵まれ、天国の姉のことを何度も話して聞かせている。
おなかの赤ちゃんに重い病気が見つかった時、家族は、特に母親は、大きな不安と恐怖に襲われます。「医療従事者も、その家族にどう寄り添っていけばいいのか分からない。踏み込んで接するのが怖く、『今回は残念でしたね』という言葉で終わってしまう。こうして家族は、医療従事者との間に溝を感じたまま、途方に暮れてしまうのです」。
広島大遺伝子診療部の産科医、兵頭麻紀さんは、多くの産科現場で見られる現状をこう説明します。遺伝カウンセリングでは、こうした母親や家族に、病気の正確な情報を伝えるとともに、自分たちで治療方針を決められるようにサポートします。そのために、こうした医療のトレーニングを積んだ産科、小児科、内科の医師や看護師、助産師らが、チームで最善の方法を考え、家族と話し合います。同部の助産師、中込さと子さんはこう言います。
「家族が自ら納得のいく医療を選択できたかどうか――。そのことが、赤ちゃんが亡くなった後の家族の心に影響します。グリーフケア(愛する人を亡くした悲嘆のケア)は、病気の赤ちゃんがおなかにいる時からすでに始まっているのです」。
日本人類遺伝学会の「臨床遺伝専門医制度委員会」のホームページには、遺伝子に関係する病気の診断や治療、カウンセリングができる「臨床遺伝専門医」の一覧が掲載されています。

陽来ちゃんのアルバムを見るA子さん

ピンクの服がよく似合う陽来ちゃん

中込さん(左)と兵頭さん
(広島大病院遺伝子診療部で)

 Home
Home