Email: koho*office. hiroshima-u.ac.jp (注:*は半角@に変換して送信してください)
山根 典子 教授
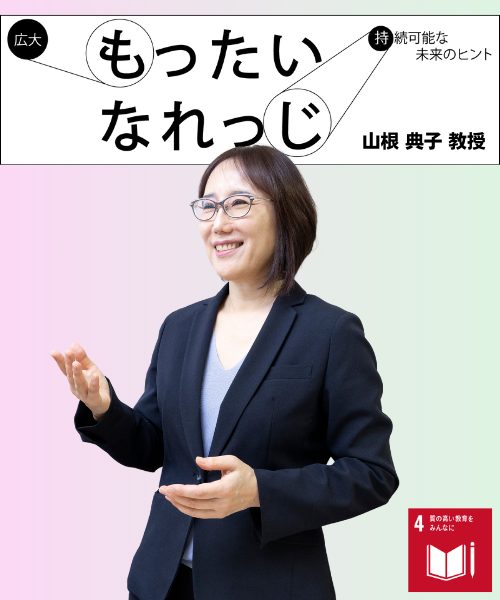
人の言語を構成するさまざまな要素
先日、スポーツバイオメカニクスのゼミと共同で、オンライン面接ではカメラを見て話した方が高評価を得られることを明らかにしました。パソコンのカメラは画面上部についていることが多いので、画面に映った相手を見て話していても、相手からは視線が合っていないように感じられてしまいます。実際にプロの面接官に評価をしてもらうと、カメラを見ていない場合はカメラを見た場合・音声のみの場合と比べて評価が低くなるという結果が得られました。
このように、コミュニケーションでは視線や手振りなど、音声以外の部分も感情や意図を伝えるうえで重要です。実は音声表現は、人のさまざまな部位の身体運動と深く関わっているのです。そのため、⾳声と意味や⽂法との関連を含め、心理や運動などの視点から学際的に⾔語にアプローチします。中でも私の専門は、人の音声の生成と知覚の仕組みについて探究する「音声学」と、意味の違いを生み出す規則を明らかにする「音韻論」。これらの分野は、言語を理解するために相互に補完し合っており、発音の学習や言語教育において不可欠となっています。
他分野と協働し、人々の悩みに寄り添う
音声データの収集技術は年々進歩しており、従来は捉えきれなかった調音動作の詳細な分析が行われています。例えば、⾳声分析ソフト、超⾳波、フェイスメッシュ、MRI、EGGなどを活⽤すれば、聴覚では聞き分けられない微細な発声や発音の違いが可視化できます。実験参加者の豊富なデータを比較分析することで、新たな規則性の発見につながっています。
言語学の面白さは、さまざまな研究に応用ができる点。私はその特性を生かし、言語教育や臨床などの分野にも貢献したいと考えています。第二言語習得の場面において、コミュニケーションの可視化は非常に重要です。舌の動きを視覚的にリアルタイムで把握できれば、日本人には馴染みのない英語の「R」と「L」など、母語と異なる発音を理解する助けになります。教育者にとっても、学習者が何につまずいているのかを知るヒントになるでしょう。また、臨床分野においては言語聴覚士や歯科医と連携することにより、発音の歪みや吃音などの問題を抱える人々に対して、より適切な支援や対応が可能になると考えています。コミュニケーションにおける困難は、身体的な病気と比べて軽視されがちですが、複眼的に取り組むことで改善の糸口が見えてくる場合もあります。いろいろな悩みを持つ人々に寄り添い、データ分析によって社会に気付きを与えるような研究を目指したいです。

検査器をのどに当てると超音波で舌の動きが見える

PROFILEやまねのりこ
- 大学院人間社会科学研究科に所属。
- 言語学、特に音声学、音韻論を専門とする。オンライン面接についての論文はScientificReportsに掲載された。
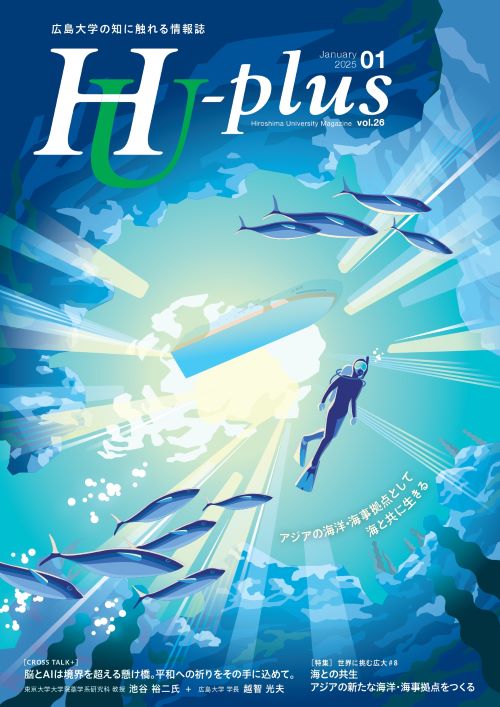
〈その他特集ページ〉
- 学長対談
東京大学大学院薬学系研究科 教授 池谷 裕二 氏
×広島大学学長 越智 光夫
「脳とAIは境界を超える架け橋。平和への祈りをその手に込めて。」 - 特集
海との共生 アジアの新たな海洋・海事拠点をつくる - AERAが書く、研究者の素顔
稲見 華恵 助教(宇宙科学センター)
広島大学広報室

 Home
Home

















