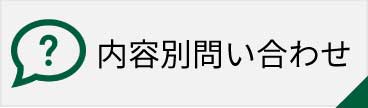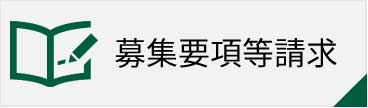広島大学は、2017年度から、教養教育の一環として、スポーツ、芸術、科学、ビジネスなど各界で活躍されているリーダーをお招きし、学部新入生を対象に講演を行っています。
本学では、大学で専門的な分野の学識を深めるのと同時に、幅広い教養、すなわちリベラル・アーツを生涯にわたって培っていくことが何より大切と考えています。
世界で活躍するリーダーたちが、どのような学生時代を過ごし、困難を乗り越えたのか。
大学での新しい一歩を踏み出す新入生に、間近で生きざまやスピリッツに触れてもらい、ワクワクする何かをつかんでもらうことを目的としています。
2024年度は、以下の方々に講義を行っていただきました。
専門分野であるゴリラの研究を中心にAIやSDGsなど幅広く話題が提供され、これまでの人類の進化や脳の発達だけでなく、デジタル化が進んだ現代においても「共感力」を育むことが大切であると説明されました。

ご専門のロシア軍研究についての背景や研究の難しさについて、日本とロシアの違い等を例に解説されました。また、ご自身の経験を踏まえ、社会の変化を予測することが難しい今、大学生のうちにいろいろな考え方に触れておいてほしいと話されました。
小学生時代に漫画家を目指し、大学時代を経て、一度は就職されたものの退職され、漫画家へ転身されたご自身の道のりを語られ、一貫性を持って目標を追求する重要性と、日々の行動の大切さについて強調されました。また、介護、震災、パンデミック、戦争などの現在社会が直面しているあるいは将来起こり得る課題についても触れ、学生たちに覚悟を持って生きることの重要性を説かれました。
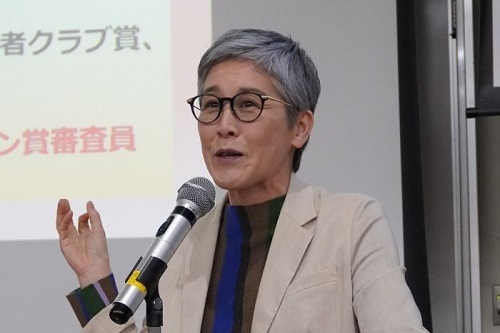
「なぜ、原爆が広島へ?」という問いをきっかけにして、膨大な取材を重ねながら執筆されたご自身の著書を紹介し、自身の足で取材を行うことへの熱意を語られました。講演に参加した学生たちは、先生の情熱や取材の奥深さを感じながら講演を聞きました。

講演の中で学生が脳の特性を体感できる内容を取り入れながら、人間の脳が身近な電磁波の一部しか見えていないことなどを例に「私たちが見ている世界とは何だろう」と学生たちに問われました。

選手の性格やコンディションなどを考慮した監督時代の指導方法や、その後広島大学大学院で学ぶ中で印象に残っているエピソード等から、他人の理論を受け入れ多様性を尊重することの大切さを語られました。
広島大学工学部の卒業生である同氏から、学生が今後の大学生活を送るにあたり、次の3つの言葉が贈られました。
(1)「そこの障子を開けてみよ、外は広いぞ」(豊田佐吉)
(2)「聞くは一時の恥、知らぬは一代の恥」 (幸田露伴)
(3)「三つの非を大切にする:非日常・非連続・非常識 」
日本とアメリカの両国を行き来して過ごした学生時代の経験を基に、教養とは何か、大学で何を学ぶべきかをお話しされました。また、世界には様々なバックグランドや価値観を持つ人が存在することをお話しされ、多様なメンバーによる議論が新しい発想を生み出し、世界が変化していくこと、それに伴い自己の価値観を広げることの大切さを語りかけました。
自身の多様な経験や活動を振り返りながら、知らないことをシェアする勇気を持ち、フラットに互いの経験を共有・交換し、元来日本が周りと力を合わせて何かをやり遂げることを得意としていたように、チームプレイを大切にしてほしいと語られました。
広島市長としてこれまで進めてこられた「まちづくり」の施策について、「広島市基本構想/第6次広島市基本計画」で掲げる三つの柱を中心に説明されました。広島市を持続可能なまちとするための取組について具体的に紹介された上で、学生に対し、個も大切にしつつ、地域の中で自分たちがどう生きていくかを意識してほしいと語られました。
ある取材で「できない言い訳を考えるのではなく、できないことにチャレンジする気持ちが大切」という言葉に感銘を受けたことを語り、学生たちに何事にも本気で向き合うことの大切さを伝えられました。また、今ある時間の尊さを学生に説き、「若い皆さんは、今なら何でもできる。なんでもやってみてほしい」とエールを贈りました。
「孤独になる事を恐れないこと」「限界を作らないこと」「同じことを繰り返す努力」など、ご自身が大切にされている考え方を整理され、学生たちにわかりやすく伝えられました。また、人との出会いが大きな転機となったことについても触れ、大学時代には「多くの人と出会い、多様な場所で経験を積んで、広い視野を持ってほしい」とエールを贈りました。
学生たちに「常に考えることが大切。考え、考え尽くしてほしい」「1人1人にできることはたくさんある。1人の力で世界を変えることができる」「人生は1度きり、広島大学の学生として誇りを持ち、何事にもチャレンジしてほしい」と数多くの言葉を贈りました。


 Home
Home