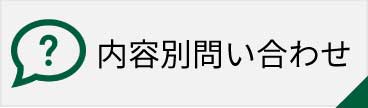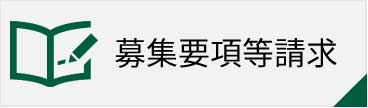広島大学は、2017年度から、教養教育の一環として、スポーツ、芸術、科学、ビジネスなど各界で活躍されているリーダーをお招きし、学部新入生を対象に講演を行っています。
本学では、大学で専門的な分野の学識を深めるのと同時に、幅広い教養、すなわちリベラル・アーツを生涯にわたって培っていくことが何より大切と考えています。
世界で活躍するリーダーたちが、どのような学生時代を過ごし、困難を乗り越えたのか。
大学での新しい一歩を踏み出す新入生に、間近で生きざまやスピリッツに触れてもらい、ワクワクする何かをつかんでもらうことを目的としています。
2023年度は、以下の方々に講義を行っていただきました。
「日本の未来にたちこめる暗雲」と題し、日本が直面している様々な課題「半導体産業での国際競争力の低下」や「加速する少子高齢化がもたらす社会のひずみ」「極東での米中関係」等について、分かりやすくお話しいただき、これから大学で学ぶ学生に向けて、こうした課題に自分たちはどう向き合っていくか考えてほしいと締め括られました。

「モーリー流 変わりゆく時代との調和」をテーマに、日本とアメリカの両国を行き来して過ごしてきた自身のユニークな生い立ちをなぞりながら、自分の夢や自分らしさを追求することの素晴らしさ、そしてその過程での苦しみや挫折にどう立ち向かうべきかを学生たちに語りかけました。
「AIで羽ばたく脳の能力」をテーマに、BCI (Brain Computer Interface) とBMI (Brain Machine Interface) の歴史と現状や、ご自身が代表を務めておられる研究プロジェクトの実験内容や成果について説明しました。専門的な内容を分かりやすく解説いただき、終始学生たちは熱心に耳を傾けていました。

「故郷の歴史を仕事にするー人類最初の原爆はなぜ広島に投下されたかー」をテーマに、これまでの取材をまとめたご自身の著書を紹介しながら、粘り強く取材を行ったことで貴重な資料が手に入ったことや埋もれていた事実が明らかになったことなどを語り、インターネット上の情報が全てではなく、自ら足を運んだり直接会って話をすることの大切さを訴えました。

「コロナの後に学ぶということ」をテーマに、コロナが終息しつつある現在、日本は経済で世界に遅れをとっていることを指摘し、今後どう立て直していくかが課題であると語りました。

「スポーツで世界に羽ばたく」をテーマに、WBCの栗山英樹監督とサッカー日本代表の森保一監督の共通点を挙げながら、過去から学び未来につなげるための歴史観や大局観、果てなき向上心を持つことの大切さを語りました。

「虫の眼、鳥の眼、時(情報)を読み解く眼」をテーマに講演を行い、物事のFACTを知るためには現在だけではなく、時間軸(歴史)を入れて考えることが大切であると述べ、県外出身者が7割を超える新入生に向けて「広島」や「ヒロシマ」を海外の人に説明できるようになるために、被爆の実相だけでなく歴史の実相を知ってほしいと語りかけました。
「人工知能革命の時代に私たちはどう生きるべきか」をテーマにした今回の講演では、ChatGPTなどに代表されるAIの近年の凄まじい進化について触れながら、AIがもたらす危険性や世界の変化について述べ、より良い未来のためにAIとどう向き合っていくべきかを問いかけました。

相手とのコミュニケーションでは「目を見て会話をする、笑顔で挨拶する、疑問に思ったことは尋ねる」の3点を学生時代にしっかりと身につけておいてほしいと強調し、最後に「入学時の志を4年間忘れることなく、目標をもって学生生活を送ってほしい」と新入生を激励しました。

「世界で活躍するまで~自分を信じる事~」というテーマで、幼少期からオペラの世界で活躍するまでを数々のエピソードとともに語りました。孤独になることを恐れない、限界を作らない、繰り返す努力をするといった自身がこれまでの人生の中で大切にしてきたことを紹介し、「夢とは計画であり、自分の行動や考え方次第で必ず叶えることができる」と力強いメッセージが送られました。
「世界に羽ばたくために必要な能力とは」というテーマにおいて、広島県副知事時代に経験した海外からの訪問者とのエピソードを紹介し、国際化に向けては多文化共生という考え方が大切であると強調しました。そのために学生時代には多くの友人を作り人脈を広げ、授業や読書によって教養を得てほしいと呼びかけました。

自らの研究人生を振り返り、大学卒業後の進路決定や留学、専門とする研究分野の選択等、人生の大きな岐路に立った時にはいつも恩師や友人らの存在に大きく影響を受けたと語り、自分を成長させてくれた人々との出会いに感謝していると話しました。
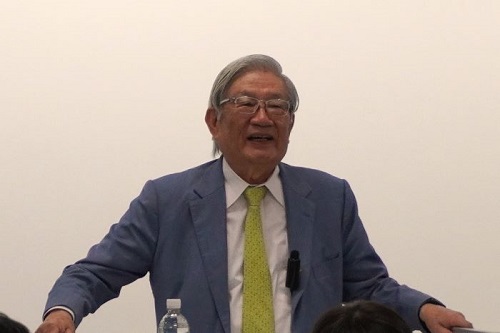
「ウクライナ危機後の世界と日本」と題し、多くの犠牲を生んだ二度の世界大戦を経ながらも、この現代に勃発したロシアによるウクライナ侵攻に至った経緯を、歴史的背景とともに解説しました。


 Home
Home