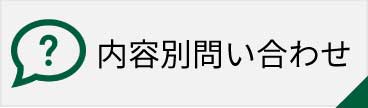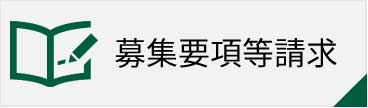広島大学は、2017年度から、教養教育の一環として、スポーツ、芸術、科学、ビジネスなど各界で活躍されているリーダーをお招きし、学部新入生を対象に講演を行っています。
本学では、大学で専門的な分野の学識を深めるのと同時に、幅広い教養、すなわちリベラル・アーツを生涯にわたって培っていくことが何より大切と考えています。
世界で活躍するリーダーたちが、どのような学生時代を過ごし、困難を乗り越えたのか。
大学での新しい一歩を踏み出す新入生に、間近で生きざまやスピリッツに触れてもらい、ワクワクする何かをつかんでもらうことを目的としています。
2018年度は、以下の方々に講義を行っていただきました。


高岡氏は考えることの大切さを強調し「社会には答えがないことが多い。大学生時代に自ら問題を探し出しその解決方法を探し出すため、自分で考え行動する力を身に付けてほしい」と話しました。

中丸氏は夏休みの科学研究に没頭した子供時代から、単身イタリアに渡りマリア・カラス国際声楽コンクールで日本人初の優勝という偉業を成し遂げ、世界の舞台で活躍するまでの歩みを語りました。
不破氏は、参加した学生に向けて「積極的に海外へ目を向け、より多くの人と出会い、様々な経験を重ねていくことが大事」とした上で「人がやっていないことに取り組むことが大事。オリジナリティーを持って、頑張ってもらいたい」とエールを送りました。

川淵氏は「夢があるから強くなる」をテーマに、講演の序盤はサッカー漬けだった学生時代や、古河電工から子会社へ出向になったことについて「人生に大きな影響を与えた」と語りました。

モーリー氏は、日米両方の学校で学んだ自身の体験を紹介しながら、多様な考え方を知ることの大切さを話しました。また、「自明と考えられていることが本当かどうか立ち止まって考えてみれば、想像力が広がる」と身振り手振りを交え、学生に熱く語りかけました。

湯崎氏は、通産省(現経済産業省)官僚をやめて通信会社を起業、そして県知事への転身に至った自身のキャリアパスについて「迷ったときは、自分の心の声に従って決断してきた。社会に貢献したいという思いが原動力」と話しました。そして、自身の経験から「キャリアは、人との関わりを通してできあがっていくもの」とし「周りを大事に、縁を大事に」と語りました。

深山氏は、広島の経済動向と課題を説明した後、「会社の成長の原点」とも語る人材育成の重要性を強調しました。「優秀な人材とは、自分の成長のために努力を続けることが出来る人。学生には、「さらなる成長のために積極的に自己啓発に励んでください」とエールを送りました。

講演は、聞き手の総合科学研究科・林光緒教授による対話形式で行われ、学生時代、プロ野球選手時代、監督時代についてのエピソードを話しました。その中で、「つらくて逃げ出したい時には、心の中のもう一人の自分に勝ちなさい。どんな経験にも無駄はない」と、身振り手振りを交え、力強く学生に語りかけました。
弘兼氏は漫画の取材で多くの国・地域を訪れた経験から、少子高齢化が急速に進む日本が抱えるさまざまな課題について問題提起しました。人類の叡智によって医療が発達する一方で、安楽死問題やゲノム編集など、人々の判断が問われていることも強調。最後に学生に「自分がどう生きるか、各々がイメージしながら過ごしていってもらいたい」とエールを送り、講演を締めくくりました。

越智学長は、自身の経歴を紹介する中で、人生の岐路となった体験談を挙げ、「人生はいつ何が起こるかわからない。常に考え、その時に備えておくことが大事」「自分一人では何もできない。先輩や後輩、友人が財産」と語り、今後の人生において、努力を惜しまないこと、国内にとどまらず様々な人達とのネットワークを築くことが大事であると話しました。

池谷教授は、「AIを迎える未来、そして脳」をテーマに講演。「AI時代が到来する2045年には今の仕事の47%は人工知能に奪われると言われるが、47%は新しい雇用が創出されると捉えるべきだ」と強調し、近年のAIの科学的な検証や論文を基に説明しました。

伊東氏は、経済の循環に比重を置いた均質な社会の中で、人と人とのつながりや人が本来持つ感受性をなくしてしまうことを危惧し、自然や地域に溶け込んだ建築物を作り出すことを通して「人を元気にしたい」と熱く語りました。


 Home
Home